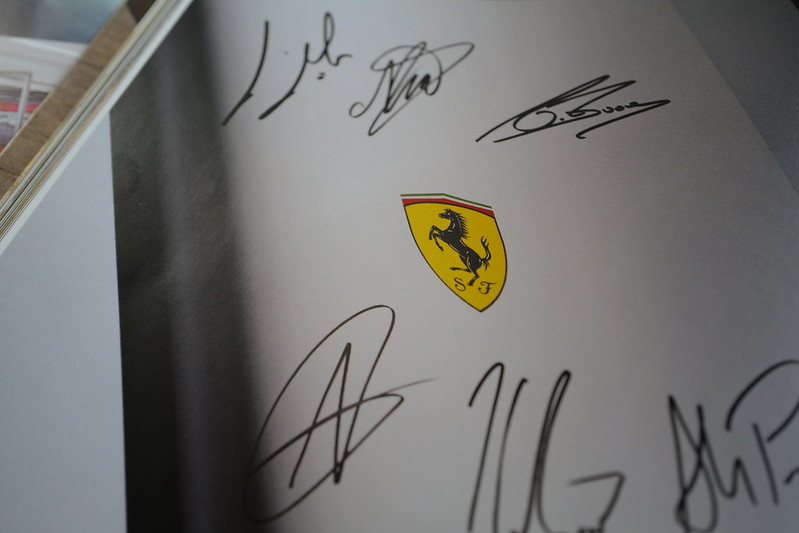| エンツォ・フェラーリは「時代の50年以上先を行く」ビジネスマンであった |
その存在は「神」にも等しく、今もその教えが根付いている
さて、フェラーリ創業者であるエンツォ・フェラーリはまことに不思議な人物で、「フェラーリ」という自動車史上もっとも強力なブランドを構築した人物である反面、「幼少期から自動車に興味があった」という記述は見られず、実際になりたかった職業としては「レーシングドライバー」を挙げているものの、そのほかにも「スポーツライター(実際に寄稿したことがある)」「オペラ歌手(本人曰く”音痴なので不可能だとわかった”)」を挙げています。
ただ、オペラ歌手はともかく、「スポーツライター」を志しただけあって文才に恵まれていたようで、さらには「文章や、文字、言葉をもっと他人を納得させ信じ込ませる」才能には非常に長けていたもよう。
-

-
フェラーリを設立し確固たるDNAを確立した男、エンツォ・フェラーリはどこでモータースポーツと出会い、どのようにして情熱を傾けるようになったのか【動画】
Ferrari / Youtube | エンツォ・フェラーリは常に技術の限界を追求し、それによって人間の能力を拡張しようとすることをやめなかった | そこには生い立ち、自身の興味、先見性など様々な要素 ...
続きを見る
エンツォ・フェラーリは優れた戦略家であった
加えて戦略家としても非常に優れた才能を見せ、ブランドという言葉が認知されていなかった時代から「ブランディング」を実践し(もしエンツォ・フェラーリがこの分野での書籍をしたためていたならば、それは現在に至るまでのベストセラーになったに違いない)、言葉巧みに有能な人材を引き抜き、そして自身に有利な記事を書くメディアや記者を選別して優遇しては自身に有利な記事を書かせたり「伝説」を作らせ、さらには様々な材料を持ち出して自身の会社を成長させるために有利な駆け引きを成功させています。※さらにはセルフプロデュースにも長けており、50年くらいは時代の先を行っていた人物なのかも
実際のところ、フェラーリ活動初期、つまりはフェラーリが町工場の域を出なかった時代に、「メルセデス・ベンツやブガッティ、アルファロメオ」といった「れっきとした自動車メーカー」にまじってグランプリを戦って勝利をあげ、そして今ではそれらを凌ぐと言われる時価総額を持つに至っており、これはまさに「神話」としかいいようがない事実です(冷静に考えると、個人のレーシングカーファクトリーが、大きな自動車メーカーにレースに挑むことは無茶であるが、フェラーリは実際に挑戦し、それらをねじ伏せている)。
こうやって見ると、エンツォ・フェラーリは「自動車好き」というよりも、「優れた戦略と分析能力を持ち、それを実現するための交渉力に優れた」ビジネスマンであったと捉えたほうがいいのかもしれず、実際に多くの「自動車好き」が興したファクトリーあるいはレーシングカーファクトリーの多く(マクラーレン、ロータス、アストンマーティン、ブガッティなど)が倒産や買収の憂き目を見ている中、フェラーリは自己資本を維持しつつも(一時はフィアットに株式の50%を持たせていたが、それでもエンツォ・フェラーリが残りの50%を保持していた)成長を続けている稀有な、もしかすると唯一の例と言って良さそうです。
そしてフェラーリが成功したのは、「クルマ好きが作った、マニアックなクルマ」が受けたからではなく、「フェラーリ」というブランドが広く知られ、そして神格化されるようになったからであり、ブランド力を極限にまで高めることができたのは、エンツォ・フェラーリが持っていた「バランスの良いビジネス、そしてプロモーションスキル」であったのかもしれません(もし、エンツォ・フェラーリがクルマに全振りされた嗜好を持っていたならば、フェラーリはあえなく倒産していたであろう)。
さらにいうならば、エンツォ・フェラーリの最終的な目的とは「フェラーリというブランドを最強にすること」であり、モータースポーツに勝利することすら”そのための手段”にしかすぎなかったのかもしれませんね。
エンツォ・フェラーリはこんな名言を残している
そして文才に優れたエンツォ・フェラーリだけあってじつに表現力にも長けており、数々の名言を残していますが、有名なのは「情熱を語ることはできない。できるのはそれを生きることだけだ」「(古巣であるアルファロメオに勝利した際に)私は母を殺してしまった」「雪の降るトリノの公園のベンチに座って落ち込んで泣いた(フィアットに職を求めたものの断られたので。これもまた自身の”成り上がり伝説”を補完するセルフプロデュースの一種であると思われる)」といったあたり。
いずれにせよ、エンツォ・フェラーリの有名な言葉とその哲学は、彼の情熱、勝利への執着、そして唯一無二のブランドを築き上げた信念に集約されますが、ここではそのほかに残された、いくつかの名言とそこから読み取れる哲学を考察してみたいと思います。
- 「子供にクルマの絵を描かせてみてください。そのクルマは間違いなく赤い色をしているでしょう。」
これは、フェラーリの象徴である「赤(ロッソ)」と、彼のブランドが持つ普遍的な魅力を端的に表すもので、フェラーリが単なる自動車メーカーではなく、人々の心に深く刻まれる存在を目指していたことが伺えます。
- 「男は娯楽を必要としない、娯楽は自分を自身の使命から遠ざけてしまうだけだ。使命があればそれで十分だ。」
彼の人生がモータースポーツとフェラーリに捧げられていたことを示す言葉でもあり、(使命の遂行を妨げる)休日でさえ彼にとっては苛立ちの原因であったとされ、常に最高を目指し、それ以外の事柄は自身の情熱を妨げるものと考えていたことがわかります(会社敷地内に住居を構えていたことからもそれは理解できる)。
- 「ジャガーはクルマを売るためにレースをする。私はレースをするためにクルマを売る。」
これは、エンツォ・フェラーリのビジネス哲学の核心を表す言葉でもあり、映画「フェラーリ」にも登場。彼は、ロードカー販売による利益をレース活動へ再投資するビジネスモデルを確立していますが、彼の目的はあくまでレースに勝つこと(それによってフェラーリのブランド価値を高めること)であり、そのための手段として市販車の販売があったわけですね。
- 「毎朝、自分のクルマに何か新しいものを搭載したい。その気持ちがスタッフを恐怖に陥れる。」
常に革新を追求する彼の姿勢を示していて、現状維持に満足せず、最高のフェラーリを生み出すためには、絶えず改善と進化が必要であると考えていたようですが、一方で「当時最先端であった」アルミホイールやディスクブレーキ、ミドシップなどを取り入れようとはしなかったという頑固な姿勢も報じられています。
なお、ドライバーやエンジニアを「恐怖」「プレッシャー」によって支配していたことでも知られており、そのためか「けしてフェラーリにワークスドライバーとして乗らなかった」レーシングドライバー(スターリング・モス、グラハム・ヒル、ジム・クラークなど)も存在します。
- 「うまくゆくには見た目も美しい車を作れ」
エンツォ・フェラーリは、性能だけでなく”クルマの美しさ”も追求しており、彼にとって「いいクルマ」とは、「機能的価値だけでなく、情緒的価値も兼ね備えたもの」であったことが分かりますね。
ポルシェ、ランボルギーニとは異なって「市販車にウイングを装着することを許さなかった」のもこのためです。
エンツォ・フェラーリはこんな哲学を持っていた
こういった数々の名言からわかるエンツォ・フェラーリの哲学は、以下の要素で構成されていると考えられます。
- レースへの飽くなき情熱と勝利への執着: 彼は人生をモータースポーツに捧げ、勝利こそが全てであると考えており、ドライバーに対しても「私のクルマに乗るなら勝つために走れ」と鼓舞し、「リスクを考慮し、2位に甘んじてポイントを持ち帰ろうとする保守的なドライバー(通常はこういったドライバーの方が好まれる)」を嫌ったという話も。
- 革新と完璧の追求: 常に新しいものを取り入れ、最高のものを生み出すことに情熱を注ぎ、現状に満足せず、細部にまでこだわり、自らの手で最高のフェラーリを築き上げようとした姿勢が伺えます(ただし、その「最高」はあくまでも自身の基準によるものであった)。
- ブランド戦略としての希少性: 「欲しがる客の数よりも1台少なく作る」というビジネス哲学によって意図的に希少性を生み出し、顧客が「何としても手に入れたい商品」と感じさせることでフェラーリの価値を高め、ここは「売れるだけ作る」というほか多くの自動車メーカーとは全く異なる方針。「目先の利益」ではなく高いブランド価値が生み出す将来の利益を見据えていたことがわかりますね。
- 「走るために儲ける」という信念: 彼はクルマを売ることが目的ではなく、レース活動を継続するための手段として市販車販売を捉えており、ロードカー部門で得た利益をレースに再投資し、フェラーリのブランド力を高めることでレースでの勝利を追求しています。そして基本姿勢は現代においても同様です。
- 職人としての誇りと責任感: 彼は「最後には自分が責任を取る」という強いリーダーシップと責任感を持っていたとされ、ドライバーやチームを鼓舞し、最高のパフォーマンスを引き出すために尽力した人物です。そのやり方には賛否あるものの、エンツォ・フェラーリを嫌う人物すら「一目置き、一定の評価を与えている」ことからも「広く尊敬を集める人物」であったことは間違いなさそうです(じっさい、「北の教皇」と呼ばれるなど、その地位は絶対的なものであったようだ)。
エンツォ・フェラーリは、単なる自動車メーカーの創業者というだけでなく、モータースポーツの歴史に名を刻む伝説的な人物であり、彼の言葉と哲学は現在も多くの人々に影響を与え続けているわけですが、実際にフェラーリの本社を訪れたり、関係者から話を聞くにいたり、ますますその認識が強まります。
通常の会社であれば、経営者が変われば「経営方針が大きく変わる」ものの、フェラーリだとエンツォ・フェラーリの「教え」が今も細部に至るまで根付いており、存命時にサプライヤーと交わした約束がいまなお守られていて、その現実に多くの人が感謝しているところを見るに、その影響力は弱まるどころか「ますます強くなっている」のかもしれません。
-

-
エンツォ・フェラーリの「工場は、人、機械、建物でできている。フェラーリは、なによりも人でできている」の精神はいまだ健在。フェラーリがホワイト企業に認定
| 創業当時のフェラーリはとにかく人材の確保に苦労しており、エンツォ・フェラーリは自ら職業訓練校を作ったほど | エンツォ・フェラーリは人に厳しかったのか優しかったのか判断がつきかねる さて、フェラー ...
続きを見る
合わせて読みたい、フェラーリ関連投稿
-

-
【フェラーリの哲学】なぜ“需要より1台少なく”しか作らないのか?エンツォ・フェラーリの信念と成功の理由
はじめに:伝説の言葉「フェラーリは常に需要より1台少なく作る」 フェラーリは常に「ブランド価値の最大化」を優先させてきた エンツォ・フェラーリは数々の名言を残していますが、最も有名なのはこの一言かもし ...
続きを見る
-

-
エンツォ・フェラーリは自分宛ての手紙にすべて返信していた!エンツォの死の直前に手紙を送った当時の子供達が40年近くを経てフェラーリ本社に招かれる
| フェラーリは排他的であり続ける一方、”ファミリー”に対しては献身的だ | 当時夢見たF1マシン、そしてフェラーリのロードカーと対面を果たす さて、毎年このクリスマスシーズンになると各自動車メーカー ...
続きを見る
-

-
フェラーリの知られざる事実15選。「エンツォ・フェラーリはアルファロメオのワークスドライバーだった」ほか
| 今となっては永遠にわからないことも | フェラーリの知られざる事実15選、という動画が公開に。フェラーリは知らないものがいないほど有名な企業へと成長したものの、けっこう謎が多い会社でもあります。そ ...
続きを見る