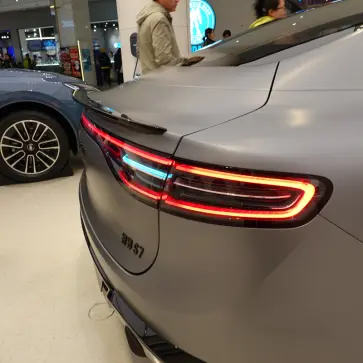| 中国の「自動車スピード革命」が世界を揺るがす |
このスピードは果たして効率化なのか、それともリスクを伴う近道なのか
多くの欧米・日本の大手自動車メーカーが警戒する中、中国ブランドが急速に追い上げを見せていますが、これは「予想だにしなかった」状況です。
その背景にあるのは「中国の自動車メーカーの驚異的な成長速度」「新車の開発・発売速度向上」ですが、たとえばBYDやChery、Zeekrなどは、従来60ヶ月かかっていた新型車開発期間をわずか18ヶ月に短縮していることが明らかになっています。
従来の常識を覆す「開発18ヶ月」
なお、一般に新型車開発は4-5年を要するのが普通であり、日米欧の自動車メーカーだとこれが「業界標準」。
しかし中国の自動車メーカーでは「平均18ヶ月」にとどまるといい、たとえばシャオミは「自動車業界へ新規参入してからわずか2年で」量産車の発売にこぎつけていて、この場合は「生産工場含め、全く経験のない状態から」のスタートであり、しかしこれは今の中国にとっては「とくに珍しくもなく、普通のこと」なのかもしれません。
- 欧米メーカー:平均開発期間は4〜5年(特にピックアップや商用車はもっと長い)
- 中国メーカー:たった18ヶ月で企画〜販売開始
- 例:Cheryは「Omoda 5」の欧州仕様を6週間でアップデート&出荷
参考までに、この「中国企業の展開の速さ」は今に始まったことではなく、たとえば(いまはもうみんな忘れてると思うけど)ハンドスピナー、セグウェイのような電動スケートボードが「一瞬で」溢れかえったことを思い出せば納得ができるかも(そして一瞬で消え去った。おそらくEV業界でも同じように多くの企業が消えるのだろう)。
中国企業はどうやって“そんなこと”ができるのか?
そこでまず「いったいなぜ中国の新興EVメーカーにとってそれが可能になるのか」を考えてみたいと思います。
ソフトウェア開発的アプローチ
- 完成度より「まず市場に出す」
- 不具合や改善点は消費者のフィードバックで対応
- シリコンバレーのスタートアップ的思考に近い
AI・仮想シミュレーションの活用
- 実車プロトタイプを省略し、VRやHIL(Hardware-in-the-loop)で検証
- Zeekr:20年分の設計データをAIで分析し部品共通化
- BYD:部品の75%を自社生産 → サプライヤー待ちリスク回避
これらのほか、「酷暑・冬季テストを簡略・省略」する例もあると聞いていますが、なによりも基本となるのは「他社に先んじられたら負け」「他者より先に出してナンボ」という基本思想なのかもしれません。
さらには「中国的・組織的特徴」も
さらに中国では(上述の通り)シリコンバレー的思想が根付いており、いわゆる「ベストエフォート型(最大限の努力はするが、失敗の可能性も許容)」を採用する場合が多く、とくに日本に多い「ギャランティー型(なにがあってもエラーが出ないように責任を持つ)」はほぼ皆無(そんなことをしていたら、製品を発売するころにはブームが収束しているか、市場を他社に抑えられチャンスを奪われてしまう)。
加えて多くの人口を抱える中国だけに「労働力を確保しやすい」「地方から安価な労働力を連れてくることができる」という特殊性も絡んでいると言われます。
加えて、中国は長らく「一党独裁」にて国を運営してきたという歴史があり、よって(ぼくが思うに)中国の「企業」においてもその性質が強く、民主的というよりは独裁によって会社が運営され、そして市場や会社が成長している段階において、その「独裁」はいい方向へと作用することが多いようですね(日米欧の企業では判断に数ヶ月かかるところ、中国企業ではその場で即決)。
中国独自の強み:「組織文化と構造」
- BYDの従業員数:約90万人(トヨタ+VWに匹敵)
- 週6日・1日12時間労働が一般的(低人件費+高稼働率)
- 階層の少ないフラットな組織 → 意思決定が爆速
中国企業の方針は「危険なショートカット」ではないのか?
確かにプロトタイプや長期実走テスト、耐久試験を省略するのはリスクが高いようにも見えます。
しかしCheryはすでにEuro NCAPで5つ星評価を取得しており、品質も国際基準に達してきているのが現実で、となるとここで思うのが「もはや多くのテストはシミュレーション上で完結するのでは」「日米欧の自動車メーカーは慣習にとらわれ、不要なことをやっているのではないか」。
もしそうだとすれば、これは「速度」だけではなく「コスト」にも影響し、中国企業は多くの面においてアドバンテージを確保しているということなのかもしれません。
日米欧の自動車メーカーはどう対抗?
現在中国の自動車メーカーは確実に世界を「侵食」しており、たとえばチェリーは2024年実績で「100カ国で110万台以上を販売」。
BYDも2030年までに販売台数の半数を国外へ輸出するという計画を打ち出しているほか、欧州と米国が設定する「関税」障壁をクリアするために現地生産を行うという計画を発表するメーカーも出ているという状況です。
つまり日米欧の自動車メーカーは「開発スピードとコストを改善しない限り」中国勢に市場を奪われてゆくだけとなる可能性も否定できず、こういった危機感からかフォルクスワーゲン、そしてアウディは中国現地企業と組むことによって「中国企業が持つ新型車開発ノウハウを吸収しようと」している段階です。
-

-
アウディが「発表したばかり」のコンセプトカーをもう生産開始。これまでに考えられないようなスピード感はやはり「中国の自動車メーカーとの合弁による賜物」か
Image:AUDI | ここからはアウディが中国にて「どう戦うのか」に注目が集まる | やはり重要なのは「値付け」であろう さて、つい先日アウディは中国向けの新ブランドとして「AUDI(すべて大文字 ...
続きを見る
長い歴史を持つ欧州自動車メーカーが、その数分の一(あるいは十分の一以下)しか運営経験がない自動車メーカーに教えを請う状況は「衝撃」以外のなにものでもなく、しかしそれが「いま自動車業界で起きていること」なのでしょうね。
-

-
やはり歴史ある自動車メーカーもEVに関しては「中国から学ぶしかない」?ルノーが中国に”はじめて”新車の開発拠点を設置し、今後さらに現地での開発を拡大するとの報道
Image:Renault | さらにルノーは現地で開発したEVを世界中へと輸出することになりそうだ | ただし現時点では「生産地」については欧州だとされている さて、現在東南アジアそして中東、さらに ...
続きを見る
合わせて読みたい、関連投稿
-

-
【フェラーリ超え?】中国・長城汽車が謎のスーパーカーを開発中。「フェラーリよりも優れ、ドーパミンが爆発するようなクルマ」
Image:Great Wall Motors | ピックアップトラックとSUVで知られる中国の自動車メーカー、GWM(長城汽車)が、ついにスーパーカー市場に殴り込み? | 実際に「新型V8エンジン」 ...
続きを見る
-

-
さすがは「中国」。EV充電用無人ロボットアームが開発され今年から実用化の見込み。さらには車両が自動でこの充電器を探して充電に行き、すべてが「無人」で行われることに【動画】
| もはや中国では自動車は「自動車ではなく」ガジェットの一種として捉えられている | 実際のところ、家電メーカーが参入し存在感を強めていることからもその傾向を見て取れる さて、様々な方面において欧米諸 ...
続きを見る
-

-
新型メルセデス・ベンツCLAには吉利汽車が開発した中国製のエンジンが積まれるもよう。さらには中国の新興企業による自立運転システムも組み込まれ、中国企業は「サプライヤー」としても重要な位置に
Image:Mercedes-Benz | もはや今の自動車業界は「中国を抜きにして」何も語ることはできない | こうやって中国は様々な業界において支配力を強めてゆくのだろう さて、メルセデス・ベンツ ...
続きを見る