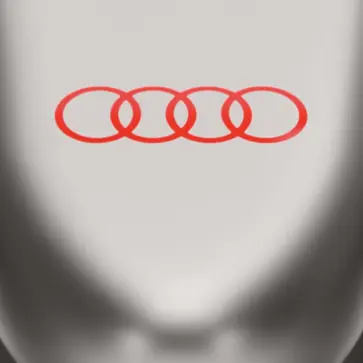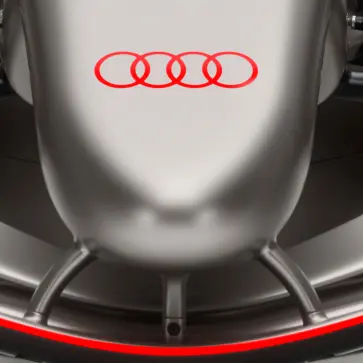| 電動パワートレーンの登場、ラインアップやボディ形状の多様化がこの現象に拍車をかける |
アウディのみならず、多くの自動車メーカーが命名には苦戦している
さて、現在多くの自動車メーカーが困っているのがその「ネーミング」。
名前を持つクルマであれば問題はないものの、メルセデス・ベンツ、BMW、アウディのように「車名が数字とアルファベット」にて構成されるクルマの場合は非常にやっかいで、これらジャーマンスリーは過去になんどか「命名法則を変更」していますね。
-

-
アウディがまたまた命名法則を変更するもよう。ややこしかった「30」「45」「70」などの数字を廃止しシンプルな名称へ。すでにQ6から新方式を採用
| アウディのみならず、BMWやメルセデス・ベンツなど「アルファベットと数字」のみによる名称を採用する自動車メーカーの車名は非常にわかりにくい | その意味では中国車の名称についてはとうてい覚えられる ...
続きを見る
「電動化」がその命名を大きく変える
そして近年、各社の命名を混乱させている要素は「電動化」。
BMWであれば「i」、メルセデス・ベンツだと「EQ」といったエレクトリックパワートレインを示す名称が既存の命名法則とうまく噛み合わず、アウディの場合だと2018年に「e-tron」が登場したのち、そのネーミング戦略は大きく変わり、そして混乱を招くこととなっています。
参考までに、アウディは1994年にそれまでの「アウディ 90」「アウディ 100」「アウディ V8」を「A4」「A6」「A8」へと置き換え、これらに加え小型モデルには小さい数字(A3)、大型モデルには大きい数字(A7)が割り当てられ、SUVには「Q」(クワトロの頭文字)という文字が与えられるように。
このほか、それぞれのモデルに「S」や「RS」という高性能なバージョンが追加され、「TT」などのごく一部の例外を除けば、シンプルでわかりやすい命名体系を持っていたわけですね。
アウディの命名は2018年から混乱が始まる
しかしながらアウディは2018年に初のEV「アウディ e-tron」を発売し、これに伴いネーミングの一貫性が崩れ始め、その後「e-tron GT」も発売されたものの、これはSUVではなくセダンタイプであり、さらなる混乱を引き起こしてしまいます。
さらには新たなEVが登場するにつれ、「e-tron」という名称がより曖昧になり、「Q8 e-tron」「Q6 e-tron」「A6 e-tron」などが登場していますが、特に「Q8 e-tron」は「Q8」と関連がないにもかかわらず、「Q8」の名を冠しており、これがいっそうの混乱を助長するといった例も。
アウディは新ルールを「撤回」
こういった事態を収拾すべく、アウディは2023年初め、「EVモデルは偶数、ガソリン車は奇数」という新ルールを発表したのですが、今回これも撤回し新しい命名法則を導入するというアナウンスを行っていて、その意図は「世界的な標準化によって顧客の混乱を解消する」。
しかしその内容はけして簡潔なものではなく、おおよそは以下の通り。
- 「A」と「Q」はこれまでどおり車種を表す(A=セダン系、Q=SUV系)。
- 数字は車両のサイズを示す(例:A6はA8より小さい)。
- ボディスタイルの名称は「セダン(Sedan)」「アバント(Avant/ワゴン)」「スポーツバック(Sportback/4ドアクーペ)」に統一。
- エンジンの種類を表す旧来のコードを復活(TFSI=ガソリン、e-tron=EV、TFSIe=PHEV、TDI=ディーゼル)。
ただし、一部の(直近で発表された)モデルはすでに車名に入る番号が変更されており、それらは元に戻せないため、モデルチェンジが行われるまでは新旧の規則が混在することになりますが、この新しい命名法則は3月に発表される次世代「A6」から実施され、たとえばA6だと「A6 TFSI(ガソリン)」と「A6 e-tron(EV)」という名称を持つことに。
さらにややこしいのは、これも少し前に用いていた「出力を示す2桁の数字を復活させる」と述べていることで、「TFSI」の前に数字が追加されるため、上述のA6だと、ガソリン版は(例えば)「A6 40 TFSI」という名称を持つことになり、ワゴンだと「RS6 アバント 40 TFSI」といった具合にかなり長い、そして命名の理由(意味)を知らない人にとってはそうとうに覚えにくい車名となってしまいそうですね。
合わせて読みたい、アウディ関連投稿
-

-
レクサス各モデルはこういった命名法則を持っている!変わり種だと「LY=ラグジュアリーヨット」、そして「S」であってもモデル間で意味が異なる
| レクサスは日本のブランドだけあって破綻のない命名法則を持っている | 欧米ブランドだと多様化しすぎて命名の意図が不明瞭になる場合も さて、各自動車メーカーはそれぞれの命名法則を持っていて、ランボル ...
続きを見る
-

-
BMWが自ら「モデルネームの数字や英文字はこう読み解く」と解説。かつてはルールがなく個別に命名されており、現在の命名法則ができあがったのは1972年
| おそらくはBMW自身、ここまでラインアップが拡大するとは考えてもみなかったのだろう | いくつかの例外はあるものの、おおよそわかりやすい命名になっていると思う さて、様々な自動車メーカーが様々な命 ...
続きを見る
-

-
アストンマーティンはなぜ「V」で始まる車名を採用するのか?「なぜなら、”V”はそのセグメントでの頂点を意味するからだ」
| アストンマーティンの「V」は1988年のヴィラージュから始まった | アストンマーティンはその車名に「V」で始まる名称を用いることで知られますが、今回Carfectionがその理由について説明した ...
続きを見る