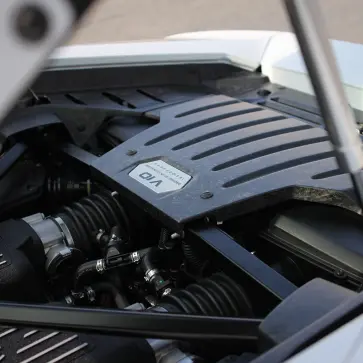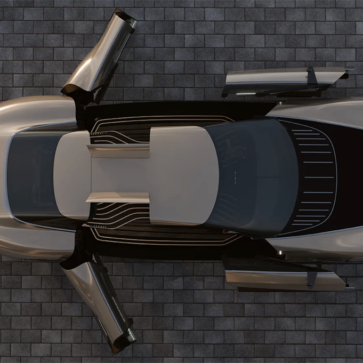| 「スマートドライビング」などの曖昧表現も禁止、OTA更新も制限対象に |
たしかに現在では「自動車メーカー各々」の表記がなされ、なんらかの規制が求められる状況に
さて、少し前にはシャオミSU7に絡む死亡事故が中国にて発生し、これを受けて中国の工業情報化部(MIIT)は、自動運転車に関する規制を大幅に強化したとの報道。
この主な目的は、消費者の誤解を招くような曖昧な広告表現を排除し、安全性を高めることにある、と報じられています。
「スマートドライビング」禁止、代わりにSAE基準を明示
今後、中国国内では「スマートドライビング」「自動運転」「インテリジェントドライビング」など、具体性に欠けるキャッチフレーズの使用が禁止され、その代わりとして各車の運転支援システムがSAE(米国自動車技術者協会)の定めるレベル0〜5のどこに該当するかを明記しなければなならなくなるもよう(各レベルの定義は以下の通り)。
多くの消費者がこの基準を知らない一方、自動車メーカー側もあえて曖昧な用語で販売促進を行っていたため、今回の措置は情報の透明化を図り、そのクルマの運転支援レベルがいったいどのあたりに位置するのかを明確に示し、ドライバーが自社の運転支援システムを過剰に信用し必要な操作を行わないなどの「誤用」を防ぐ意図があるようですね。
- レベル0:支援機能なし
- レベル2:現在主流のADAS(例:テスラのFSD含む)
- レベル3:メルセデス・ベンツのDrive Pilotが唯一認定
- レベル5:完全自動運転(現時点では市販されていない)
その他の新ルール一覧
- スマート召喚(リモート・サモン)機能の全面禁止
→ テスラの“スマート・サモン”など、ドライバーが乗っていない状態で車を動かす機能は禁止 - ドライバーモニタリングの無効化不可
→ ドライバーが60秒以上ハンドルから手を離した場合、車は自動で減速・停止・ハザード点灯 - ADAS機能のパブリックベータテスト禁止
→ 一般ユーザー向けにソフトウェアを試験的に提供する行為は違法に - OTAアップデートの頻度を制限
→ 頻繁な機能追加は、想定外の挙動やトラブルの元になると判断
これらの措置は、つい最近中国で発生したシャオミ SU7による死亡事故をきっかけに講じられたもので、報道によると、半自動運転状態からドライバーが操作を再開した直後、車両が時速約100kmで電柱に激突し3名が死亡するという痛ましい事故であったとのこと。
今回の中国の規制強化につき、「やりすぎ」と見るか「妥当な判断」と見るかは意見が分かれており、ただ、自動運転技術の進化にともなって法整備の必要性が高まっているのは間違いなく、運転支援デバイスについては消費者保護と透明性のバランスが問われる時代に突入し、自動車メーカーが「誤認を生じさせる」表記に関し全世界的に規制の対象となる時期に差し掛かっているのでしょうね。
合わせて読みたい、関連投稿
-

-
激動の自動車業界では2025年に何が起きるのか?中国では「大量倒産」「合併」「欧米企業と中国企業の提携解消」「自動運転や全固体電池の導入」が予想される
| 中国は「自動車の販売における主戦場」から「技術の中心」へと移り変わる可能性がある | まさに誰も予期し得なかった変化がここにある さて、現在変動著しい中国の自動車市場。そのトレンドは他の国や地域と ...
続きを見る
-

-
BYD傘下のジーカー(Zeekr)がレベル3相当の高度な自動運転システムを発表、中国EV市場の競争の中心は”自律運転”に
Image:Zeekr | 自動運転は開発に多大なコストがかかり、小規模メーカーはここで「ふるい」にかけられるのかも | 現時点ではジーリーが最も先進的、時点ではBYDか ジーリー(Geely)傘下の ...
続きを見る
-

-
ついに中国にて自動運転(FSD)の提供を開始したテスラ。メディアのテスト中にライバルの「倍以上」となる34件もの交通違反を記録し”課題の多さ”が浮き彫りに
| さらには「ドライバーが介入せねばならない状況」もライバルより多く記録 | ただしここからテスラはデータ収集と分析を重ねることで精度を増すものと思われる さて、つい先日テスラは中国において「完全自動 ...
続きを見る