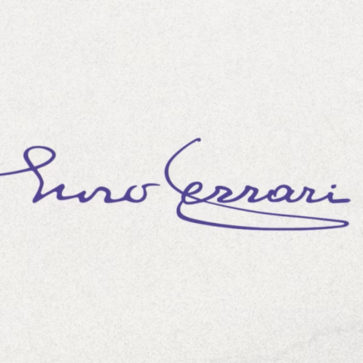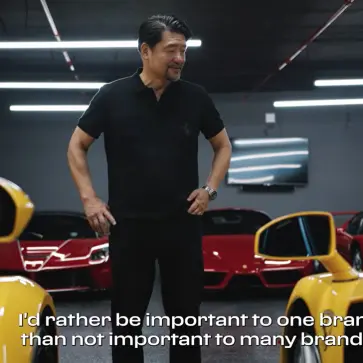| フェラーリといえば「ミドシップ」、そしてV8という認識も強い |
もともとエンツォ・フェラーリはミドシップには「批判的」であったが
さて、現代のフェラーリにおいてもっとも高い人気を誇るレイアウトが「ミドシップ」であることに異論はないかと思いますが、もともとエンツォ・フェラーリはミドシップレイアウトには批判的であった人物です。
そのため、1950年代に登場しF1グランプリを席巻するようになってからもなかなかミドシップを取り入れようとはせず、ようやくこの流れに合流したのが1961年の「フェラーリ 156 F1」。
なお、エンツォ・フェラーリは以下の点においてミドシップを敬遠していたと言われています。
- 伝統と哲学: エンツォ・フェラーリは、クルマに積まれるエンジンのトルクを全身で感じ、操る喜びを味わうべきだと考えており、これをもっとも体現できるレイアウトが「フロントエンジン」だと考えていた※「牛車は牛が押すものではなく、牛が引っ張るものだ」という言葉を残しており、色々な意味で”エンジンファースト”であったのかもしれない
- 安全性への懸念: エンジンがドライバーの背後に配置されるため、衝突時の安全性に不安を感じていたとされ、特に熱いエンジンや燃料タンクが近くにあることへのリスクを危惧していた
なぜフェラーリはミドシップを採用したのか?
しかし、なぜ最終的にミドシップを採用したのかというと、それは彼の「勝利への執念」が、他のあらゆる哲学や懸念を上回ったから。
つまり、エンツォ・フェラーリにとって「勝つこと」ことこそが最も重要であり、そのためには信念や哲学までをも変更してしまうという柔軟性を持っていたということを意味していますが、これは彼が「実は頑固者ではなかった」という側面を示唆しています。
ただ、一般的に「頑固者」だと認識されている背景には、この「ミドシップをなかなか取り入れなかったこと」、そして「アルミホイールやディスクブレーキの導入すらも遅かったこと」、そしてこれらについて「周囲の進言を聞き入れなかったこと」に起因しているのかもしれません。
つまり、時代が代わり、「ミドシップ」「ディスクブレーキ」「アルミホイール」がモータースポーツにおける主流になりつつある中、エンジニアがどれほど「これらを取り入れるよう」主張しても、断固としてそれに応じなかったのがエンツォ・フェラーリ。
-

-
英国伝統の自動車メーカー、ロータスの誕生から現代に至るまでの歴史を考察。コーリン・チャップマンの残した功績はあまりに大きく、しかしその天才性に依存しすぎた悲運とは
| 「ロータス」は創業者であるコーリン・チャップマンの画期的な思想によってその名を知られるように | とくに「軽量」「ハンドリング」はそのブランドの”核”である 自動車の世界において「ロータス」という ...
続きを見る
このあたり、率先して新技術を考案し、F1だけではなく幅広くレーシングカー、そして市販車において「革命」を起こしてきたロータス創業者、コーリン・チャップマンとは真逆の姿勢です。
これは「エンツォ・フェラーリはエンジニアではなくレーシングチームの運営責任者であり、コーリン・チャップマンは優れた知識と技術を持つエンジニアであった」からだとも考えられ、エンツォ・フェラーリが古い技術に固執したのは、「エンジニアリング上のチャレンジによってチームの成績を落とすことはできない」と考えていたからなのかもしれません。
これがエンツォ・フェラーリを「枯れた技術、しかし信頼性があり、(それまで)優位性が実証されていた技術」へと固執させていた可能性があり、要は「レースに安定して勝つため、あえて危険性を冒してまで最新の(不安定で信頼性が確立されていない)技術を採用しなかった」のでは、とも考えられます。
実際のところ、エンツォ・フェラーリは一時を境に「ミドシップ、アルミホイール、ディスクブレーキ」などの技術を次々と取り入れることになるのですが、これは「それらの新しい技術が、リスクなく優位性を発揮できるようになった」と判断したからなのだと思われます。
言い換えれば、エンツォ・フェラーリは「機が熟す」のを待っていたということになりそうで、満を持して投入した初のミドシップマシン、1961年の「フェラーリ 156 F1」は当時のF1レギュレーション変更(排気量制限)に合わせて開発されたクルマであり、ミドシップの技術的な優位性を最大限に活用下設計がなされ、その結果として1961年シーズンはドライバーズチャンピオンシップとコンストラクターズチャンピオンシップの両方を獲得し、フェラーリにダブルタイトルをもたらしています(かなり長い時間をかけミドシップカーをテストしていたのだと思われる)。
こういった経緯を見るに、エンツォ・フェラーリは「チームを成功に導くため」長期的な視点で様々なものごとを捉えており、条件が揃うまではリスクを踏まないという慎重さをもっていたこともわかりますね。
エンツォ・フェラーリは、自身の哲学や信念に固執する頑固な一面があったものの、それは単にノスタルジーや思い込みによるものではなく、彼なりの「勝利への方程式」に基づくものであり(ちゃんと合理的な理由があった)、しかしその真意が理解されず、他者の考え方をはねつけるという一つの面だけが誇張されることで「エンツォ・フェラーリは頑固で古臭い考え方を持つ人間」だという誤解を生んだのかもしれません。
そして新技術を導入する判断もまた「勝てるかどうか」という現実的なファクターによるもので、「勝てる」とわかればそれまでの方法論をあっさり捨てていることは、彼が何よりも「速さ」と「勝利」を追求する求道者であったことを示しています。
フェラーリもミドシップの時代へそしてこの156 F1の成功をもってフェラーリは本格的にミドシップへと移行することになり、これはモータースポーツのみではなく「ロードカー」においても同様です。
そしてフェラーリにとって初の「ミドシップレイアウト採用の市販車」は1967年の「ディーノ206GT」で、ただしこれは”フェラーリ”ではなく”ディーノ”ブランドからの登場なので、”フェラーリブランド”というくくりだと、それは1973年の365 GT/4 BB。
ディーノ206GTは、優れたハンドリングと走行性能で高い評価を得ることとなり、この成功が、エンツォ・フェラーリ自身のミドシップに対する認識を変えるきっかけになったとも見られているのですが、ここから「フェラーリブランド」のミドシップカーが登場するまでに6年を要していることからも、エンツォ・フェラーリが「極めて慎重な人物であった」ことが伺えます(成功を急がず、むしろ失敗によるブランドイメージ毀損を恐れたのかもしれない)。
なお、この「365 GT/4 BB」が搭載していたのは「V12エンジン」で、「V8エンジンを搭載する初のミドシップフェラーリ」となると、それは1975年にデビューした「308 GTB」です。
308 GTBから始まったフェラーリV8ミドシップの歴史
1975年にデビューしたフェラーリ308 GTBは、マラネッロに革命をもたらした存在として記録されていて、それは「フェラーリの市販車としては初めてミドシップレイアウトとV8エンジンを採用し、その後50年にわたって続く血統の礎を築いたから」。
ピニンファリーナによってデザインされた308 GTBは、フラット12を搭載するBBシリーズと共通するデザイン言語を持ちつつ、よりコンパクトで軽快なスタイルを実現し、特徴的なエッグクレートグリルと4灯テールランプがこの時代のフェラーリらしさを象徴しています。※F8トリブートでは、V8フェラーリの歴史へのオマージュとして、この「丸4灯」が復活している
搭載された3.0リッターV8は横置き配置が選択され(市場や排ガス規制によって異なるが、最高で255馬力を発生)、1980年にはインジェクション仕様、1982年には4バルブ仕様が追加されています。
初期モデルは軽量なグラスファイバー製ボディを採用していたことがよく知られ、しかしこれはのちに(生産性の問題から)スチール製へと変更されることに。
さらに1977年にはオープントップのGTSスパイダーが追加され、この「クーペとスパイダー」という構成は、それ以降の世代でも継承される「スタンダード」となっています。
1985年:フェラーリ 328 GTB
308 GTBから10年後に登場した328 GTBは排気量を3.2リッターへ拡大し、最高出力は270馬力に向上。
乾燥重量1263kgと軽量で、0-100km/h加速は6.4秒を誇ります。
デザインはより空力を意識したソフトなウェッジシェイプとなり、テール周りも丸みを帯びた造形へと進化したほか、インテリアもアップデートされ、より洗練されたドライビング体験を提供したモデルとして知られます。
1989年:フェラーリ 348 TB
328 GTBが進化型であったのに対し、348 TBはフルモデルチェンジに相当する存在で、テスタロッサを彷彿とさせるサイドストレーキを採用したことが外観上の大きな特徴。
シャシー構造も刷新され、リアにはパワートレインと後輪を収めるサブフレームを備えたスチール製プラットフォームが用いられたほか、エンジン(300馬力を発生する3.4リッターV8)が初めて縦置きレイアウトに変更されるなど、メカニカル面において大きな進歩を遂げています。
1994年:フェラーリ F355 ベルリネッタ
1994年に発表されたF355ベルリネッタは、348をベースに大幅な改良を加えたモデル。
サイドエアインテークのデザインはストレーキを廃止し、より洗練された現代的な造形へと進化していますが、テールランプも4灯を維持しつつ、よりクリーンでシャープな印象へ。
-

-
フェラーリF355シリーズは今年で発売30周年。フェラーリいわく「おそらく、F355はもっとも特別、そしてもっとも重要なV8モデルです」。その理由とは
Ferrari | フェラーリF355はデザイン面ではエレガンス路線へと回帰、しかしエンジニアリング面ではエアロダイナミクス含め大きな飛躍を果たしている | さらにははじめて「F1」トランスミッション ...
続きを見る
排気量は3.5リッターに拡大し、さらに1気筒あたり5バルブという新技術を採用していますが、これは当時のF1マシン「F1-89」から着想を得たもので、8250rpmで380馬力を発揮するというパフォーマンスを誇ります。
なお、ギアボックスは伝統的なゲート式マニュアルに加え、初のF1パドルシフト(セミオートマチック)が設定されたことも見逃せないポイントですね。

あわせて読みたい、フェラーリ関連投稿
-

-
「北の教皇」とまで呼ばれ、その権力を絶対的なものとしたエンツォ・フェラーリ。どのような名言を残し、どのような哲学を持っていたのか?
| エンツォ・フェラーリは「時代の50年以上先を行く」ビジネスマンであった | その存在は「神」にも等しく、今もその教えが根付いている さて、フェラーリ創業者であるエンツォ・フェラーリはまことに不思議 ...
続きを見る
-

-
エンツォ・フェラーリの教え:「2位は最初の敗者である」。勝ったときよりも負けたときのほうが機嫌が良く、”敗北から学ぶことで”フェラーリを最強へと導く
| エンツォ・フェラーリの勝利への飽くなき探求心 | 意外なことにエンツォ・フェラーリは「負けても」怒らなかったと記される エンツォ・フェラーリはひたすら「1位」を目指し、「チームとポイントのことを考 ...
続きを見る
-

-
エンツォ・フェラーリの生涯:創業からフェラーリのF1参戦、上場までの軌跡をたどる。フェラーリのエンブレムがはじめて装着されたのは創業よりも早い1932年7月9日
| エンツォ・フェラーリの生涯とフェラーリ創業の歴史 | フェラーリの伝説はいかにして形作られたのか 世界的スーパーカーブランド「フェラーリ」。その礎を築いたのが、創業者エンツォ・フェラーリ(Enzo ...
続きを見る
参照:Ferrari