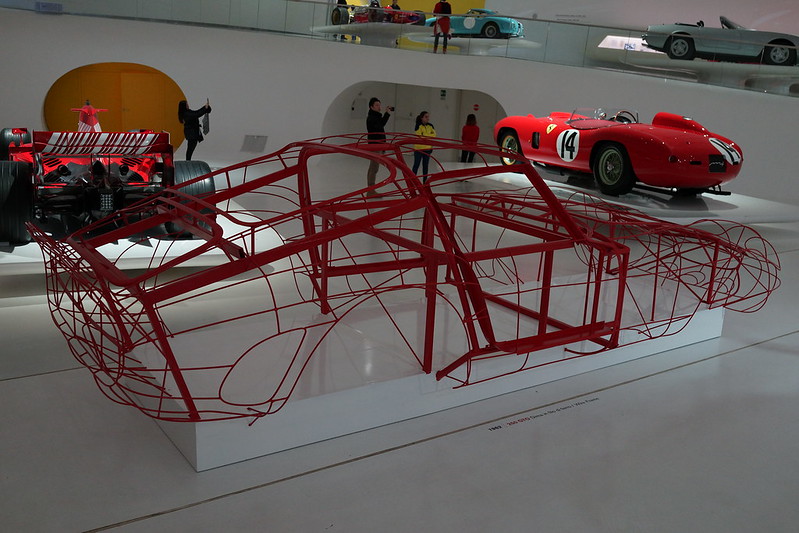| エンツォ・フェラーリは理解が難しい人物ではあるが、その実「非常に単純」なのかもしれない |
大きな「軸」はフェラーリというブランドを守ることにある
さて、フェラーリ創業者、エンツォ・フェラーリの人物像を探るシリーズ、今回は「後編」。
エンツォ・フェラーリは強いカリスマ性を誇ったことでも知られますが、その「(サングラスで隠された)仮面」の下には一人の人間としての脆さ、そして企業人と父親としての二面性も伺えます。
-

-
知れば知るほど「ナゾ」である。フェラーリ創業者、エンツォ・フェラーリとはどういった人物であったのか?その言動から人物像、そして考え方を探ってみよう(前編)
| そもそも何故モータースポーツの世界へと足を踏み入れたのかもわからない | いち「個人」が自動車メーカーに対抗できるチームを立ち上げ、成長させるなど謎が深まる フェラーリの創業者として知られるエンツ ...
続きを見る
エンツォ・フェラーリは「前に進むために踏みとどまる」事ができる人物であった
「前編」では”枯れた技術”を好んだことに触れましたが、それは頑固であったからではなく、確率として「フェラーリにとって勝てる可能性が高かったから」。
つまり何でもかんでも新しいものにチャレンジするというわけではなく、着実に勝てる可能性を考慮し、しかもその可能性は「一般論」ではなく「自分たちのチームにとって」という論理的な思考によって導き出されたのだと考えられます。
要するに、なにがなんでもライバルと競うのではなく、自分たちのスケールやリソースを考えた「背伸びをしない」判断を行うのがエンツォ・フェラーリであったというわけですね。
こういった面は「感情的」「激情型」と評されることが多い彼の人物像とはやや異なるもので、もうひとつ「イメージと異なる」のが「レースで負けても怒らなかったこと」。
エンツォ・フェラーリはレースの際にサーキットに出向かず、本社入って左側の執務室にてテレビやラジオ経由にてレースの経過を知ることを常としていたそうですが、意外なことにレースに負けても激怒することはなく(もちろんスタッフはレースに負けてエンツォ・フェラーリが怒り狂うのではないかと恐れていたそうだ)、むしろ「負けたときのほうが」機嫌が良く、これは最初のレースで負けた際に「幸先の良いスタートだ」と言ったこと、「2位は最初の敗者である」としてすぐさまマシンの改良に取り掛かったことからも事実であったとわかります。
こういった面を見ても、エンツォ・フェラーリのトッププライオリティは「勝つこと」にとどまらず「勝ち続けること」「最終的な勝者になること」にあったのだと考えられ、長いタームで物事を捉えていたようですね。
そしてこういった長期的な視点が「新しい技術に飛びつかない」という余裕を生み出していたのかもしれません。
そのほか、エンブレムについても「適切なときに」使用を開始しており、有名な「バラッカ伯爵の母から授かった」後、すぐにこれを使用せず、1923年6月17日に「跳ね馬」を賜ったものの、初めてこれを使用したのは1932年のスパ・フランコルシャン24時間レースにて。
-

-
エンツォ・フェラーリの生涯:創業からフェラーリのF1参戦、上場までの軌跡をたどる。フェラーリのエンブレムがはじめて装着されたのは創業よりも早い1932年7月9日
| エンツォ・フェラーリの生涯とフェラーリ創業の歴史 | フェラーリの伝説はいかにして形作られたのか 世界的スーパーカーブランド「フェラーリ」。その礎を築いたのが、創業者エンツォ・フェラーリ(Enzo ...
続きを見る
ただしこのときエンツォ・フェラーリはアルファロメオに在籍していたので「8C」への掲出となり、実際に「フェラーリ」の名を冠したクルマに取り付けられたのは1947年の「125S」。
この際にはシールド型ではなく「長方形の」エンブレムとなっていますが、エンツォ・フェラーリはこのエンブレムのデザインについて芸術家とともに慎重にデザインを行い、「Ferrariの文字の上を、馬が飛び跳ねて浮いているように」等の細かい指示を与えています。
-

-
フェラーリが公式にそのエンブレム誕生を語る。エンツォとミラノの芸術家によって作られ、文字の上で「馬が跳ねているように」というのはエンツォの指示だった
| フェラーリが公式にエンブレムについて語るのはおそらくこれが初だと思われる | フェラーリの「馬」は現在に至るまでに「スリム」になっていた さて、フェラーリは自動車業界でもっとも印象的なエンブレムを ...
続きを見る
こちらも「採用までに」長い時間を要しているものの、「適切なときに、適切な武器を取り出して戦える」というエンツォ・フェラーリの(直情的ではない)戦略的な一面を見ることができそうですね。
エンツォ・フェラーリは独特の美学を持っていた
前編でもエンツォ・フェラーリの美学について触れましたが、その美学はいたるところで発揮されており、例えばマシンの美しさだけではなく「工場敷地内の駐車方法」にも現れていて、欧州は一般的に「前から突っ込む」前方駐車(下の画像)が一般的であるのに対し、フェラーリの敷地内では「(日本でおなじみの)バックで停める後方駐車」。
これは単に「前方駐車は美しくない」という理由だからだそうですが、実際にフェラーリの本社にゆくと「来訪者も含めて後方駐車」となっており、創業当初から守られている伝統の一つということになりそうです。
そしてこういった「伝統を守ること」には意味があり、というのも小さなことであっても「それを守る」ことがルールを決めた人への尊敬と理解につながるから。
そして「約束を守る」というのもエンツォ・フェラーリの自身に対する美学のようなもので、「約束を反故にする」という話もチラホラ聞かれるものの、自身に忠誠を尽くす人に対する約束はちゃんと守っていたもよう。
-

-
【教育への情熱】フェラーリは「学校」を創っていた。エンツォ・フェラーリが支援した「未来のエンジニア」を育てる職業訓練校とは
| 以外なことに「北の教皇」が最も投資したのは、機械ではなく「人間」だった | そういった関係もあって「モデナ」にはスーパーカーに詳しい人材や企業が多い フェラーリ創業者「エンツォ・フェラーリ」。 冷 ...
続きを見る
たとえば、フェラーリの車体はかつて(すべてではなく、250系などが中心であった)スカリエッティにて製造されていましたが、このスカリエッティは現在、フェラーリに完全に買収・所有されており、フェラーリのアルミ合金車体を製造するメイン工場として稼働しています。
- 役割: 近年の「296 シリーズ」や「SF90」、「12チリンドリ」などのアルミ製シャーシやボディシェルは、今もこの旧スカリエッティ工場で、伝統的な職人技と最新のロボット技術を融合させて作られている
- 伝統の継承: 「叩き出し」によるアルミ整形の技術は、今もフェラーリのレストア部門(フェラーリ・クラシケ)などで受け継がれている
ただ、興味深いのは、現在は「フェラーリの車体工場」となったにも関わらず、公式に「カロッツェリア・スカリエッティ(Carrozzeria Scaglietti)」の名が残されていること。
これはスカリエッティがフェラーリに会社(と工場)を譲り渡す際に「スカリエッティの名を残して欲しい」と頼み、エンツォ・フェラーリがそれを承諾したためで、この「男と男の約束」がいまに至るまで生きているというわけですね。
これら「バック駐車」「スカリエッティ」については、ぼくが実際にフェラーリ本社を訪問した際にフェラーリの社員から直接聞いた話なのですが、エンツォ・フェラーリ死してなお、従業員がこうした話を「誇らしげに語る」ことが印象的です。
エンツォ・フェラーリは自分ですべてをコントロールしたかった
一方、エンツォ・フェラーリ自分の意にそぐわない行動をするもの、自分に背くものに対しては容赦ない対応を行うことでも知られており、エンツォ・フェラーリに「もの申した」重鎮をまとめて解雇した”宮廷の反乱”はその最たる例。
そのほか、メディアに対しても、「フェラーリに否定的な意見を述べる」記者は徹底的に排除されたそうですが、これはエンツォ・フェラーリが当時の新聞や雑誌を隅々までチェックし作成された「ブラックリスト」によって執行され、これは今で言うところの「エゴサーチ」にも通じるものがありそうですね。
なお、こういった行動を「自分に反対するものを感情的に処分した」と捉えることも可能であり、しかしぼくとしては「戦略的に行った」のだとも考えていて、その理由は様々な行動を見るに、「エンツォ・フェラーリの目的はフェラーリというブランドの価値を最大化することにあり、それが一切ブレなかったから」。
-

-
エンツォ・フェラーリの教え:「2位は最初の敗者である」。勝ったときよりも負けたときのほうが機嫌が良く、”敗北から学ぶことで”フェラーリを最強へと導く
| エンツォ・フェラーリの勝利への飽くなき探求心 | 意外なことにエンツォ・フェラーリは「負けても」怒らなかったと記される エンツォ・フェラーリはひたすら「1位」を目指し、「チームとポイントのことを考 ...
続きを見る
そしてブランド価値を形成するのはレースでの勝利であり、勝利を阻む要素は徹底的に排除し、そして勝利のためには自分自身で完全にコントロールできる環境を構築したかったから」だとも考えています。
そのために「自分の意見を聞き入れる」エンジニアやドライバーを雇い入れ、フェラーリに否定的な意見を述べる記者を排除して「好意的な意見を書く」ライターを優遇したのだというわけですね。
さらに言えば、エンツォ・フェラーリは「1位になるのが無理であった場合、安全に2位で完走してポイントを持って帰ろうとする」ドライバーを嫌悪したといい、これは「勝ち負けどうこう」よりも、(エンツォ・フェラーリの考える)ベストを尽くしていないと判断されたからなのかもしれません(あるいは、安全策を取るのがフェラーリだという印象を人々に与えたくなかったからか)。※余談ではあるが、外観上の特徴だと、小柄でハンサムなドライバーが好まれたという
-

-
フェラーリを設立し確固たるDNAを確立した男、エンツォ・フェラーリはどこでモータースポーツと出会い、どのようにして情熱を傾けるようになったのか【動画】
Ferrari / Youtube | エンツォ・フェラーリは常に技術の限界を追求し、それによって人間の能力を拡張しようとすることをやめなかった | そこには生い立ち、自身の興味、先見性など様々な要素 ...
続きを見る
参考までに、エンツォ・フェラーリは「負けること」をネガティブに捉えていないと述べましたが、映画やドキュメンタリーにおいても「負けるシーン」を使用することにはOKを出し、しかしNGだったのは「フェラーリが抜かれるシーン」。
同じ「負ける」にしてもそのプロセスの違いがエンツォ・フェラーリにとっては「天と地ほど差がある」ということだったのかもしれず、このあたりもやはり「人々に与える印象=ブランディング」を考慮したものだと考えられます。
とにかく「自分ですべてをコントロールしたかった」のがエンツォ・フェラーリだと考えているのですが、これは「公共交通機関に乗りかがらなかった」という点にもその性質が現れているように思われ(電車や飛行機に乗っての移動をひどく嫌った)、というのも同じ距離と区間を移動するにしても、「自分の意思で移動したり、自分の運転で移動するのと、公共交通機関で”運ばれる”のとは全く意味が違うから」。
傍から見ると「結果は同じ」ではあるものの、本人にとっては「全く違う」ということになり、この違いを理解出来ない場合、その人にとってエンツォ・フェラーリは「理解不能でエキソントリック」だと映るのかもしれませんね。
リスクを受け入れ、未来を創ろうとした
そして「すべてを自分のコントロール下に置きたい」という極めて強い欲求は、裏返せば「最高の成果を残すためにはそれしかない」という目的意識の現れだとも捉えることができ、ここを理解しておくとエンツォ・フェラーリの行動の大部分を理解できるようにも思います。
つまるところ、結果や運命を人任せにせず、すべてのリスクを自分で引き受けて未来を築こうとした男、それがエンツォ・フェラーリその人。
そしてその行動にブレや迷いはなく、その純粋さ、求道者っぷりが(それを理解できる人の)心を動かし信頼を集めるのだとも思われます。
なお、人を「クルマの交換可能な部品のように」使い捨てたという印象もあるエンツォ・フェラーリではありますが、(スカリエッティのように)自身に忠誠を誓った人物は手厚く保護する傾向があり、レースで負傷したり死亡したドライバー、そして遺族に対しては誠意を示し、そしてファンから寄せられた手紙にはすべて目を通し、直筆にて返事を書いたというエピソードも。
これらはある意味では「二面性」のようにも感じられ、しかしその軸(行動原理)となっているのは「フェラーリというブランドを大切にしているかどうか」であるとも考えられ、そしてこの軸は現代における「限定モデルの割当(招待)」にも反映されているのかもしれません(お金で購入権利を買うことはできない)。
こうやって見るならば、クルマ自体はエンツォ・フェラーリの時代から大きく変わったものの、フェラーリという会社の中に流れる「血」は当時と変わっていないのかもしれませんね。
合わせて読みたい、フェラーリ連投稿
-

-
なぜポルシェとフェラーリはエンブレムに「同じ馬」を使用しているのか?そのロゴに隠された「歴史ミステリー」とは
| 知られているようであまり知られていないのが「フェラーリとポルシェのエンブレムの「馬」は同じルーツを持つという事実である | この記事の要点まとめ ポルシェの馬: 創業の地、ドイツ・シュトゥットガル ...
続きを見る
-

-
「北の教皇」とまで呼ばれ、その権力を絶対的なものとしたエンツォ・フェラーリ。どのような名言を残し、どのような哲学を持っていたのか?
| エンツォ・フェラーリは「時代の50年以上先を行く」ビジネスマンであった | その存在は「神」にも等しく、今もその教えが根付いている さて、フェラーリ創業者であるエンツォ・フェラーリはまことに不思議 ...
続きを見る
-

-
【フェラーリの哲学】なぜ“需要より1台少なく”しか作らないのか?エンツォ・フェラーリの信念と成功の理由
はじめに:伝説の言葉「フェラーリは常に需要より1台少なく作る」 フェラーリは常に「ブランド価値の最大化」を優先させてきた エンツォ・フェラーリは数々の名言を残していますが、最も有名なのはこの一言かもし ...
続きを見る