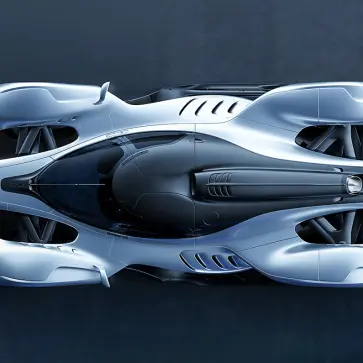| かつて「電気式パーキングブレーキ」は一部の高級車にのみ許される装備であったが |
いまやほとんどのクルマが「電気式パーキングブレーキ」に
かつて運転席と助手席の間にあった”力強く引き上げるレバー式”、あるいは足元のペダルを踏み込む”足踏み式”のサイドブレーキ(パーキングブレーキ)。
これらは「クルマの常識」であったものの、しかし今、多くの新車には指先で操作できる小さなスイッチしか見当たらず、なぜ、ほとんどの自動車メーカーは、この歴史ある機械式のシステムを廃止し、電子式パーキングブレーキ(EPB)へと移行したのか、という疑問が湧いてきます。
この変化の裏側には「単なる最新技術の採用に留まらない」、安全性、設計の自由度、そしてドライバーの快適性を劇的に向上させるなど複数の明確な理由が存在し、ここでは電気式パーキングブレーキ=EPBが自動車業界で標準装備となった背景、そしてその革新的なメリットを解説します。
ケーブルが不要に:機械式の抱える課題とEPBの登場
パーキングブレーキは駐車時、特に傾斜地で車両の動きを確実に止めるための重要な安全装置であり、MTのみではなくAT車であっても(坂道駐車時には)トランスミッション内部の摩耗を防ぐために使用が推奨される機能です。
1. 機械式の限界:老朽化とメンテナンスの手間
従来の機械式パーキングブレーキは、物理的なレバーまたはペダルがスチールケーブルを介して後輪ブレーキ(多くはディスク)に接続されていましたが、こ構造は単純ながらも「長年の使用や環境にさらされることで」以下のような課題が生じます。
- ケーブルの伸びや摩耗: 定期的な使用によりケーブルが伸びたりほつれたりしてブレーキの効きが悪化
- 固着・錆びつき: ケーブルや機械部品が錆びつき、特に寒冷地では固着して解除できなくなるリスクが発生
- 操作力の問題: 腕力や脚力が弱い人には操作が困難な場合があり、不確実なブレーキ力になる(そうなると、坂道などでクルマが動き出すことも)
2. EPBの登場と進化:ケーブルからの脱却
電子パーキングブレーキは2001年のBMW 7シリーズ(E65)で初めて採用され、当初はスイッチ操作で後部の作動モジュールがモーターを動かし、従来のケーブルを介してブレーキを作動させるという構成を採用しています。
しかし現代のEPBはそこから大きく進化し、ブレーキキャリパーに電動アクチュエータが直接取り付けられた完全な(ワイヤーを介さない)電子制御システムが主流となり、これにより、老朽化や環境によるケーブルの故障リスクが完全に解消されたわけですね。
EPBがもたらす革新的な付加価値と空間効率
EPBが高級車から一般車まで急速に普及した決定的な理由は、「快適性」と「自動化機能」を車両に付加できる点にもあり、まとめてみると以下の通り。
1. 快適性と安全性の向上
EPBは単にブレーキをかけるだけでなく、ドライバーの操作ミスを防ぎ、「確実に」パーキングブレーキを作動させることが可能です。
さらにはこれと組み合わせた様々な機能が登場しており、これらによって「ドライバーの疲労軽減」「事故防止」など様々な恩恵を(ぼくらドライバーは)受けています。
| メリット | 詳細 |
| オートホールド(Auto Hold) | 信号待ちなどで停止した際、ブレーキペダルから足を離しても停止状態を維持(ホールド)可能。アクセルを踏むと自動で解除され、特に渋滞や坂道発進での疲労が軽減される。 |
| 自動作動/解除機能 | エンジン停止時の自動パーキングブレーキ作動、および発進時の自動解除により、かけ忘れや解除忘れによる故障リスクを防止する。 |
| 緊急ブレーキ機能 | 走行中にドライバーが意識を失うなど緊急事態が発生した場合、同乗者がEPBスイッチを操作することで、緊急停止機能として作動させることが可能となる(車種による)。 |
| アダプティブ・クルーズコントロール(ACC)との連携 | EPBと連携することで、渋滞追従型のACCがより長時間、確実に車両を停止状態に保持できるようになり、システム全体の快適性と安全性が向上する。 |
2. 室内設計の自由度の向上
さらにはEPBの採用によってレバーやペダル、さらには物理的なケーブルが不要になるかわり、「室内には小さなスイッチを配置すればいいだけ」に。
これにより、センターコンソール周辺の空間を広々と活用することが可能となり、収納スペースの拡大や、よりモダンで洗練されたインテリアデザインが可能となっています。
結論:EPBへの移行は自動車の進化に「必須」
結論として、電子パーキングブレーキの普及は、自動車が単なる機械から「ソフトウェア定義型車両(SDV)」へと進化する過程で不可欠なステップであり、操作の確実性、故障リスクの低減、そして何よりも「オートホールド」に代表される快適な自動制御機能の提供こそが、EPBが業界標準となった最大の理由だとされています。
そしていま、多くのクルマでは「P」レンジに入れて駐車すると自動的に電子式パーキングブレーキが作動し、エンジンを始動させてアクセルを踏めば「自動解除」。
つまりパーキングブレーキを操作する機会すらなくなりつつあり、今後の自動車業界では「パーキングブレーキ」という概念すら消え去ってしまうのかもしれません。
ただ、ちょっと気になるのはそこまでの「移行期」で、たとえば完全に自動化された電気式パーキングブレーキを装備するクルマにしか乗ったことがない場合、その人が「手動式パーキングブレーキ」のクルマに何かの拍子で乗ったりすると、「パーキングブレーキのかけ忘れ」「パーキングブレーキの解除し忘れ(それでも走れる場合がある)」が考えられることで、これらはいくばくかの危険性をはらみます。
ただ、こういったリスクも「安全なクルマ」へと移行する一つの「織り込み済みの事案」であるとも考えられ、全体としてみるとそう大きな問題ではないのかもしれません。
あわせて読みたい、関連投稿
-

-
BMWはなぜM3とM5に「リアドアとフェンダーのツラが合わず段差がある、不整合な」デザイン採用しているのか?──デザイン責任者が語る”違和感” “レーシングカーらしさ”の美学とは
| M3とM5との「後部ドアとリアフェンダー」はツライチではなく段差がある | やはりBMWは「議論を呼ぶ」デザインが大好きである BMWの現行M3およびM5は非常に高いドライビングパフォーマンスを持 ...
続きを見る
-

-
ポルシェはなぜターボチャージャーを持たないクルマ(EV)にターボグレードを用意し、ターボを持つガソリン車の一部を「ターボ」と呼ばないのか
Image:Porsche | 「ターボ」の半世紀──911からタイカン、マカン /- 開園EVにまで続く革新と伝統の象徴 | ポルシェ「ターボ」という名が持つ意味 今から半世紀以上前、ポルシェは91 ...
続きを見る
-

-
【自動車デザイン革命】なぜ「スプリット・ヘッドライト」が世界を席巻するのか?:その背後にある技術進化とブランドアイデンティティ戦略とは
| イントロダクション:自動車の「眼」が失われた時代へ | もはや自動車デザインの中心は「スプリットヘッドライト」へ かつて自動車のフロントエンドでは、左右の角に配置された大型のヘッドライトがその顔つ ...
続きを見る
参照:Jalopnik