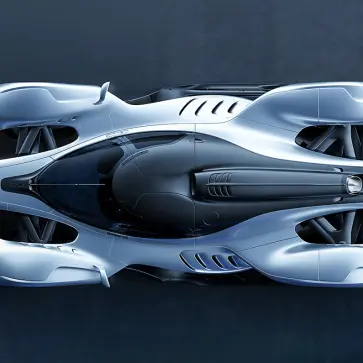| イントロダクション:自動車の「眼」が失われた時代へ |
もはや自動車デザインの中心は「スプリットヘッドライト」へ
かつて自動車のフロントエンドでは、左右の角に配置された大型のヘッドライトがその顔つきを決定づけていましたが、今日の自動車は全く新しい「眼」で世界を見ています。
それはバンパー上部に細く鋭く光るLEDデイタイムランニングライト(DRL)であり、そしてバンパー内に隠されるか、ボディワークにシームレスに統合された「スプリット・ヘッドライト」です。
SUV、セダン、ステーションワゴンまで、多くの車種で採用が広がるこのデザインは、単なる一過性の流行ではなく、すでに定着し、さらに拡大を続ける大きな流れでもあり、この機能と造形の分離がいかにして自動車メーカーのデザイン戦略、ひいてはブランドのアイデンティティを再定義しているのかを考察してゆきたいと思います。
Ⅰ. 「スプリット・ヘッドライト」が普及した科学的・技術的背景
まず、この革新的なデザインが普及した最大の要因はLED技術の進化にあります。
逆に言えば、LED技術の進化なくしてはスプリットヘッドライトは成り立たず、自動車デザイナーがずっと行いたかったことが「LED技術の進歩によって」可能になったと言い換えることもできそうですね。
1-1. DRLの「デザインステートメント」化
最初に考えねばならないのはヘッドライトと「スプリット」されたもう片方の存在、つまりデイタイムランニングランプ。
これはかつてヘッドライト内に組み込まれることが多かったものの(初期の頃は光源がLEDではない)、LED技術の小型化・高効率化によってLEDの採用が主流となり、LEDの持つデザイン的自由度に後押しされる形によって、デイタイムランニングライト(DRL)は単なる安全機能から、クルマの顔を決定づけるデザインの主役へと変貌しています。
- 造形の自由度: LEDチップのサイズが極めて小さいため、デザイナーはDRLを「発光するデザイン要素」として、バンパー内に、細くシャープなラインとして自由に配置できるようになった
- 視覚的求心力: 高いデザイン性とともにバンパーへと組み込めるようになったDRLは、クルマを印象づける光のシグネチャーとして機能し、即座にそのブランドを識別させるグラフィックエレメントとなった
- 法的な要件:LEDデイタイムランニングライトの配置・デザインにおける自由度は非常に高く、しかし「より高い」自由度を持たせようとなると、法規で定められるヘッドライトの位置に従った場合、その自由度が阻害される場合が出てきた(よって、ヘッドライトから独立させることにより自由なデザイン性を獲得できる)
1-2. メインライトの「隠蔽」を可能にした技術進化
一方、夜間の視界を確保するハイビーム/ロービームといった主要ヘッドライトは、(やはりLED技術・照射コントロール技術の進化によって大きなリフレクターが不要となって)小型化・高効率化が進み、もはやフロントエンドの角に巨大なユニットとして配置する必要がなくなっています。
- 技術的要請の克服: LED技術は、発光面が小さくても必要な光量を確保できるため、メインライトをバンパー下部やエアインテーク部といった目立たない位置に隠蔽することが可能になった
- 元々は「技術的解決策」: スプリットデザインは、元々は技術的な要請(例:特定のコンセプトカーにおける高さを活かしたデザインの実現、ヘッドライトの隠蔽による未来的な雰囲気の演出)に対する巧妙な解決策として誕生したものの、今や明確なスタイル選択要素となっている
Ⅱ. ブランド戦略としての「光の言語」
さらにこのスプリット・ヘッドライトは、自動車メーカーにとって新しい視覚言語を確立するための強力なツールとなっています。
2-1. 既存概念を破壊する過激なデザイン
- フェラーリ・プロサングエ(Purosangue): ほとんど見えないほど細いDRLを巨大なエアインテークの上に配置することで、大胆かつスポーティな造形を際立たせ、技術と空気力学の融合を極限まで追求
- ランボルギーニ・レヴエルト(Revuelto):ランボルギーニの主要デザイン言語「Y」を主張し、ひと目でブランドを認識させることに成功
- ヒョンデ・コナ / ツーソン: このセットアップを中心に視覚的アイデンティティ全体を構築し、DRLをフルワイド(ボディ幅いっぱい)にしたり、グリルに統合することで、従来の枠に囚われない未来的・グラフィック的な顔つきを作り出している
- BMW 7シリーズ:ヘッドライトを「隠す」ことでライティングエリアを最小限にとどめ、これによってキドニーグリルを更に大きく見せ、高級車にふさわしい”威圧感のある”存在感を主張
- トヨタ・クラウン:ヘッドライトを「隠し」、フォーク状のDRLを強調することにより、トヨタ車共通のフロントマスク「ハンマーヘッド」を実現
2-2. ヘリテージを継承する統一的なサイン(シトロエン、ランチア)
- シトロエン C5 X: 2016年のコンセプトカー「C-Xperience」に端を発し、ブランドの象徴であるダブルシェブロン(山形紋章)にハイマウントライティングシグネチャーを統合し、主要ライトを下に隠すことで、フランス車特有のエレガンスと未来感を両立させている
- ランチア・イプシロン: 聖杯をモチーフにしたブランドの紋章に呼応するハイマウントLEDを採用し、エレガントなフロントエンドを実現
Image:Lancia
-

-
新型ランチア・イプシロン正式発表。新世代のデザインをまとい、インテリアは「カッシーナ」とのコラボレーション。願わくば日本でも販売してほしいものだが
LANCIA | ランチアはここしばらく「イタリア国内のみの販売、車種はイプシロンのみ」だったが | 今回の新型イプシロンは欧州全土で販売予定 さて、ランチアが「13年ぶりの新車」、イプシロンを正式発 ...
続きを見る
2-3. 光を繋げる「コネクティブ・エレメント」としての活用
スプリット・ヘッドライトと並行して、連続的するライトストリップもトレンドのひとつ。
- VW ID.4、クプラ・タヴァスカン:左右のDRLを一本のLEDストリップで接続し、横方向の広がりと統一感を強調
- テスラ・サイバートラック: 連続した水平LEDストリップを唯一の視覚的な光のシグネチャーとし、実際のヘッドライトはバンパー内の目立たない垂直モジュールに完全に隠蔽するという最も過激な解釈を示している。新型モデルYも同様の手法を採用
Ⅲ. 自動車の「顔」の未来:EV時代とアイデンティティの表示
スプリット・ヘッドライトの流行は、自動車デザインにおけるより大きな変化、すなわちEV化とグリルレスデザイン時代の到来を象徴しています。
3-1. ラジエーターグリルからの解放
EVの台頭により、冷却のための伝統的なフロントグリルは役割を失いつつあり、その結果としてクルマのフロントエンドはエンジン冷却のための構造から解放され、アイデンティティを表示するための”ディスプレイ”へと変化しています。
Image:Mercedes-Benz
-

-
メルセデス・ベンツ「ヴィジョン・アイコニック(Vision Iconic)」発表。ソーラーペイントや巨大発光グリルを備え”未来と伝統を融合した”ド迫力のコンセプトカー
Mercedes-Benz | これまでのメルセデス・ベンツとは全く異なるデザイン言語を押し出してきた | メルセデス・ベンツ、「Vision Iconic」で“新しいアイコンデザイン時代”を宣言 メ ...
続きを見る
3-2. 光の表現力:アクティブな装飾へ
この新しい時代において、光はもはや単なる技術的な機能(照明)ではなくなります。
- 表現要素: 光はブランドのシグネチャー、動的な装飾、コード化された言語へと進化。アウディ Q6 E-TronやBMW i7のように、超薄型LEDユニットが断片化された宝石のようにデザインされ、ダイナミックな点灯シーケンスを可能にする例も
- デジタルディスプレイ化: BMW i Vision Deeのようなコンセプトカーは、従来のヘッドライトをインタラクティブなLEDパネルに置き換え、デジタルディスプレイとして機能させる未来を示唆。HiPhi、Xpengなどの中国ブランドは、形状や色、シーケンスを変化させられるライトの実験を進めている。メルセデス・ベンツ・ヴィジョン・アイコニック、AMG GT XXも同様である
結論:存在感が薄くなるヘッドライト、存在を主張するDRL
ヘッドライトがその純粋な技術的役割を離れ、より小さく、より控えめに、そしてほとんど見えないものへと変化する一方、DRLを中心とする光のシグネチャーは、より”前面”に移動し、鋭く、表現豊かになっています。
自動車の「眼」がよりプレゼンスを強めるというデザイン革命は、自動車の顔つきが技術進化と市場戦略によって再構築されていることの明確な証拠であり、クラシックな「眼」を持つクルマは急速に過去のものとなりつつあるのかもしれません。
あわせて読みたい、関連投稿
-

-
かつてのスーパーカーの代名詞、ポップアップヘッドライトはなぜ「禁止されていないのに」消滅したのか?そもそもの生い立ち、そして消滅の理由を考える
| 近年、ポップアップヘッドライト(リトラクタブルヘッドライト)は別の形で一部復活しつつある | やはりスーパーカーにポップアップヘッドライトは欠かせない さて、ポップアップヘッドライト(あるいはリト ...
続きを見る
-

-
フェラーリのデザイナーが「ヘッドライト」について語る!ボクは常々「フェラーリのヘッドライトはコロコロ変わるのに、なぜどれもフェラーリに見えるのか」が不思議だった
| とくにフェラーリのヘッドライトのデザインはF12でLEDを採用して以来、大きく変化した | さらにはその複雑さは他の自動車メーカーの追随を許さない フェラーリは「世界で最も美しいSUV」と評される ...
続きを見る
-

-
これで中国人は見分けがつくのか・・・?最新の中国車はどれもデザインや車名が似すぎていてボクにはさっぱり区別がつかない。なぜそうなったのかを考えてみた
| 中国のビジネスにおける基本戦略は「差別化」ではなく「模倣」である | よってヒット商品が出ればすべて「右へ倣え」に さて、ぼくがいつも思うのが「最近の中国車はどれも同じようなデザインばかりになって ...
続きを見る
参照:Motor1