
| AI向けのプロンプトを、AIの立場と特性を理解して考えることによって自分自身が「AI寄り」に |
現実として、「言語と人格」とが連動するという仮説があるようだ
さて、現在はなにかとSora 2やナノバナナなど「AI」が話題となっていますが、何の因果なのか、現在ぼくの業務の多くは「プロンプトの作成」に費やされています。
ぼく自身はテクノロジー推進派なので、AIの活用についてはなんの抵抗なく、プロンプトの作成も比較的楽しみつつ行っているものの、ここでぼくにとっての「ちょっと困ったこと」が生じることとなっているわけですね。
-

-
AIが普及し始めたいま現在。この時点ですでに「AIに呑まれて思考を停止する人」と「AIを活用し自身の限界を押し広げる人」とに分かれてきたな
| AIと人間はそれぞれの得意分野が異なり、お互いが補完する存在だと考えている | ただしすでに「AIに取って代わられた」人がいるのも確かである さて、ここ最近話題となっているのが「AI」。ぼくも様々 ...
続きを見る
AI的考え方の導入によって人格が変わる
その「ちょっと困ったこと」とは、プロンプト作成に没頭すると人格が変わってしまうように感じるということで、これは「バイリンガル(またはマルチリンガル)における人格の変化」や「言語と自己(セルフ)」といったテーマで長年研究されているものの一種かもしれません。
簡単に言うと、一つの言語を話している時と、別の言語を話している時で、態度、思考、感情の表現の仕方などが変わるという、多くのバイリンガルやマルチリンガルが経験する現象であり、プロンプトという「AIとの会話のための言語」を使用することで、日常的に使用する言語を話すときの自分とは異なる人格へと変化してしまう、というわけですね。
AIへの命令に際しては「AI向けの専用言語」が必要である
ちょっとした検索や調べごとであれば問題はないものの、ぼくが依頼されているプロンプトは「高度にビジネスに特化したもの」で、そのためにAIへの指示(命令)、調査や評価を行う項目、その判定基準、出力形式などを事細かに「文字で」行うことに。
通常、「対人」であればこういった命令は「文字で、しかも一度の指示で」行うことはないと認識していあますが、AIの場合はそうではなく、よってAIが「間違えないよう、求める方式で、もれなく調査や評価を行うように」命令せねばならず、そのため言い回しや文章の構成が非常に特殊なものとなってしまい、これは「AIとの対話のための、専用の言語」と捉えることができるのかもしれません。
そしてこういった「AIに理解できるようにものを考え、命令書(プロンプト)を作る」という作業はぼくを「AI的な人間」にしてしまうようで、折に触れて「あ、いまの考え方(や発言)はAIっぽいな」と自分で気づいたりする場面も。
もともとぼくは人間性を持ち合わせない、プログラムされた人間のようだと評されることが多いのですが(身を切っても血が出ないだろうと言われる)、これでまた一歩「ロボットに」近づいたようにも感じます。
さらに、こういった「その言語に付随して人格が変わる」現象につき、たとえば「日本語と英語」「日本語と中国語」であれば、言語そのものがガラリと変わるので「人格もスパっと」切り替わるのですが、「日常会話とAIとの会話」には日本語を使用しているため、しばらくAIと対話していると「なかなか日常の、人間との会話向けの人格」に戻れないこともあり、これにはちょっとした危険性すら感じるところ。
こういった現象が「学問的に確立された」わけではないが
こういった現象に直接対応する一つの簡潔な専門用語、あるいは学問的分野(たぶん)があるわけではありませんが、関連する心理学や社会言語学の概念としては、以下のようなものが挙げられます。
- 言語的相対論(サピア=ウォーフの仮説): 個人が使用する言語によって、その個人の思考様式や世界観が影響を受けるという理論。これは、言語が変わると性格が変わるという感覚の背景にある、より大きな枠組みと考えられる(映画「メッセージ」の主なテーマである)。
- 文化的な要因と社会的な期待: 言語は、それが話される文化や社会的なルールと密接に結びついていて、例えば、日本語を話す時は「空気を読む」といった社会的な期待から自己抑制が働きやすい一方、別の言語ではより自己主張しやすい、といったことが変化の要因とされる。
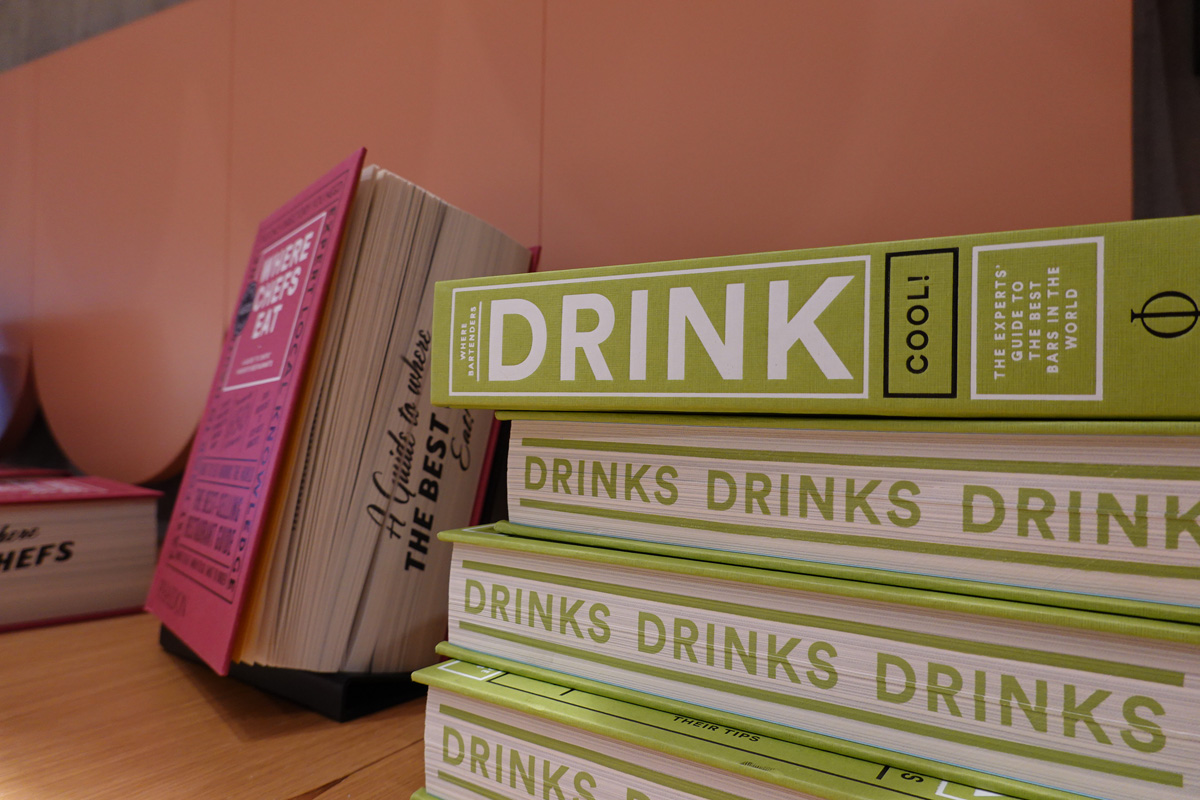
これらの現象は、「使う言語によって、その言語が持つ文化やコミュニケーションスタイルに適応し、結果として振る舞いや自己の見せ方が変わる」と理解されることが多いようであり、今後AIがぼくらの生活、そしてビジネスの一部になるに際し、ぼくと同様に感じる人も少なからず出てくるのかもしれません。
あわせて読みたい、関連投稿
-

-
ボクは80%までしか目指さない。その理由は「0から80%まで仕上げるのは容易だが、80%から100%にまで仕上げるのは容易ではないから」
| そもそも100%はこの世に存在せず、その基準は人によって変わるのだから、それを追求してもムダである | であれば「80%」にとどめておき、100%を目指すための労力を別のことにかけたほうがずっとい ...
続きを見る
-

-
ふと自分の人生を振り返る。たぶんもう一度人生を与えられたとしても、ボクは今以上にうまくやれるという自信はない
| つまり、今の人生において、ボクは「けっこううまくやったんじゃないかな」と考えている | 思えばぼくの人生はちょっとした「錬金術師」のようなものであった さて、よく「人生やり直せたら」とはよく言われ ...
続きを見る
-

-
ボクは幸運を掴んだとしても素直に喜ぶことができない。さらに褒められることも認められることも「得意ではない」
| おそらく、ボクは降って湧いた幸運に「自分がそれを受け取る資格がない」と考えているのだと思う | やはり自分自身の力によって勝ち取らないと「自分のもの」として喜べない 世の中の多くの人が「褒められた ...
続きを見る














