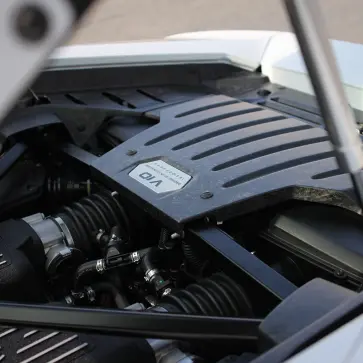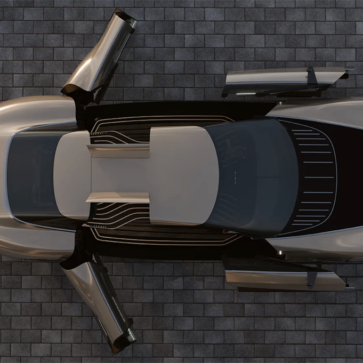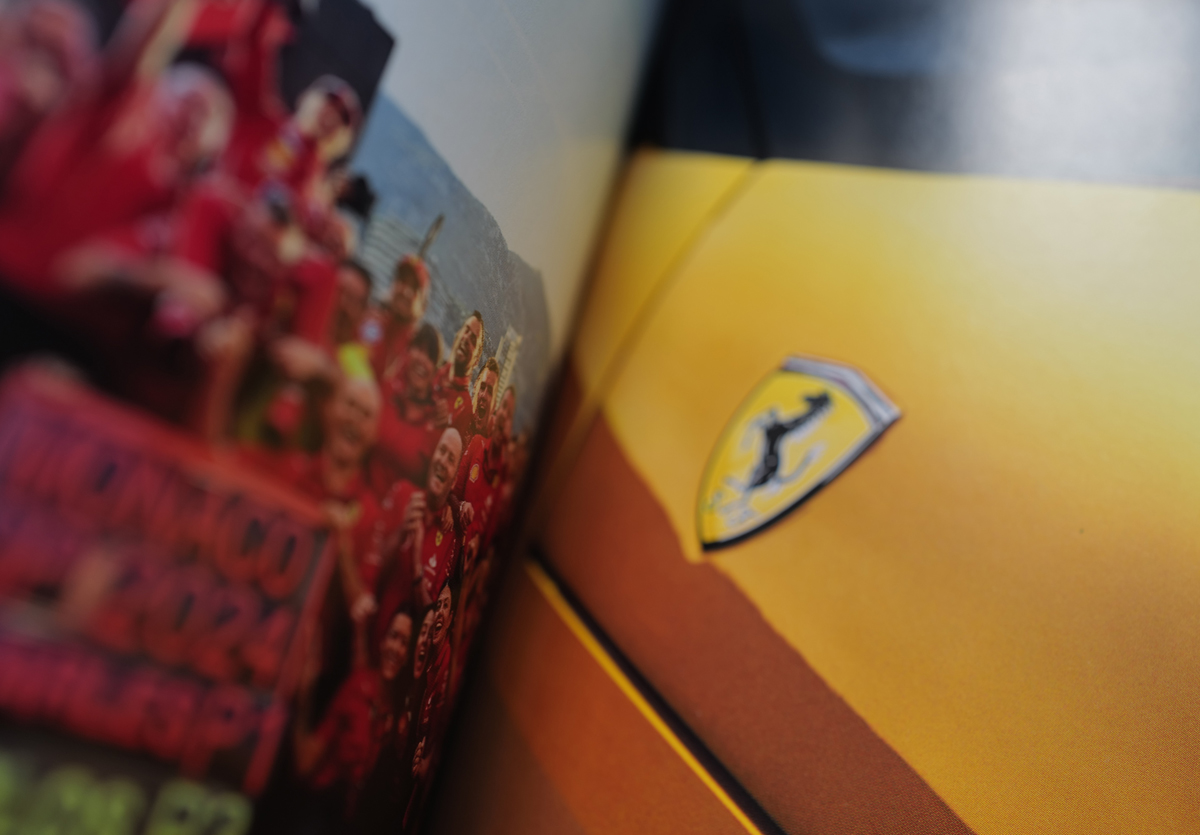
| いまや失われつつある「ナショナルカラー」ではあるが |
そのナショナルカラーにはこういった起源がある
かつてのレーシングカーの車体色には「単なるデザイン以上の意味」があり、たとえばフェラーリの象徴である「レッド」、メルセデス・ベンツの「シルバー」、そしてホンダの「アイボリーにレッド」など。
これらは単なる色やその組み合わせではなく、モータースポーツの深い歴史と、国や企業の誇りが詰まった「ナショナルカラー」と呼ばれるものです。
ここでは、このナショナルカラーが一体なぜ生まれ、どのようにして今の形に変わっていったのか、その壮大な物語を紐解きつつ、F1黎明期の国威発揚の時代から、現代の商業主義と技術革新がもたらした変革まで、レースカーの「色」にまつわる知られざる歴史と最新の動向を徹底的に掘り下げてみたいと思います。
第1章:色の起源―なぜ国旗ではなく「ナショナルカラー」が生まれたのか
1.1. ナショナルカラーの誕生:ゴードン・ベネット・カップ
自動車レースの歴史は、1900年代初頭に国威をかけた戦いとして始まっており、その象徴的なイベントが1900年から1905年にかけて開催された国別対抗レース「ゴードン・ベネット・カップ」。
このレースは自動車の性能だけでなく、国の技術力や工業力を競う場であり、参加国を明確に識別するためのルールが設けられ、それが各国のマシンに特定の「色」を割り当てるというもので、これが今日のナショナルカラーの直接的な起源とされています 。
Image:Mercedes-Benz
この初期の割り当ては、現在多くの抱くイメージとは大きく異なっていて、例えば、開催国であるフランスは伝統的な「ブルー」を選んだものの、ドイツは「ホワイト」、アメリカは「レッド」、そしてイタリアは「ブラック」。
イギリスは「グリーン」を選択し、ベルギーには「イエロー」が割り当てられていますが、当時のナショナルカラーを見ると、「イタリアのレッド」や「ドイツのシルバー」といった、現在当たり前となっている色が当初は存在しなかったことがわかり、この事実は、ナショナルカラーが最初から決まっていたものではなく、時代や出来事によって変遷してきたことを物語っています。
-

-
ブリティッシュ・レーシング・グリーンの起源とは?1903年のゴードン・ベネット・カップにまで遡ることができる伝統カラー
| ブリティッシュ・レーシング・グリーンは自動車業界において最もアイコニックなカラーのひとつである | そしてボクの好きなボディカラーのひとつでもある 「ブリティッシュ・レーシング・グリーン(BRG) ...
続きを見る
1.2. 伝説のカラーへ:各国の象徴的な「色」の確立と変遷
ゴードン・ベネット・カップを皮切りに、各国のナショナルカラーは勝利の歴史や伝説的なエピソードを経て確固たるアイデンティティを確立していきます。
イタリアン・レッド(Rosso Corsa)
イタリアのナショナルカラーは、当初「黒」が割り当てられていたものの、ゴードン・ベネット・カップの開催中に「赤」へと変更。
この「赤」は、その後、当時レースに参戦していたアルファロメオやマセラティといったイタリアのメーカーによって引き継がれ、最終的にフェラーリの代名詞となっていますが、現在では、フェラーリを象徴するこの「赤」は「ロッソ・コルサ(レース・レッド)」と呼ばれ、イタリアのモータースポーツ界を象徴する色として世界中に定着しています 。
ブリティッシュ・レーシング・グリーン
イギリスのナショナルカラーである「緑」は、開催国であるフランスへの敬意から、国旗の色である赤、白、青を避けて選ばれたとされています 。
当初はオリーブ色(ネイピア・グリーン)であったものの、アイルランドでのレース開催にちなみ、アイルランドの国花であるシャムロック(クローバー)、アイルランドの守護聖人である聖パトリックに経緯を表して現在の「深いグリーン」へと変化したとされ、このやや暗めの緑は、ベントレーやジャガー、アストンマーティン、そしてチーム・ロータスといった数々の名門チームによって受け継がれ、「ブリティッシュ・レーシング・グリーン」という固有名詞として、今もなお語り継がれています 。
Image:Lotus
フレンチ・ブルー(Bleu de France)
フランスは、ゴードン・ベネット・カップの主催国として伝統的な「青」をナショナルカラーとして選択し、この色は、ゴルディーニ、タルボット、そして現代のアルピーヌや過去のリジェ、プロストといったフランスのコンストラクターに引き継がれ、フランスのモータースポーツの伝統を象徴する色として根付いています。
Image:Alpine
シルバーアローの誕生とドイツの変革
ドイツのナショナルカラーは、もともと「白」。
しかし1934年のアイフェル・レースに参戦したメルセデス・ベンツが、車体重量の規定をわずかにオーバーしてしまうという事態に直面し、その際、チームは苦肉の策として、白い塗装をすべて剥がし、銀色のアルミ地をむき出しにして重量を規定内に収めるといった対策を取ることに。
結果として、そのマシンは見事に勝利を収め、この伝説的なエピソードから、メルセデスは「シルバーアロー(銀の矢)」と呼ばれるようになり、ドイツのナショナルカラーは「銀」として定着しています。
この出来事は、単なるルール順守のための実用的な判断が、その後のナショナルカラーのアイデンティティを決定づける物語となったことを示しています。
Image:Mercedes-Benz
日の丸カラーの挑戦:ホンダと本田宗一郎の秘話
日本のモータースポーツの象徴であるホンダが、F1に初参戦した際、日本のナショナルカラーとして「白地に日の丸」を選択。
これは当時ドイツが「白」をナショナルカラーとしていたため、明確な差別化を図る必要があったためですが、この決定には”より深い裏話”が存在します。
ホンダの創業者である本田宗一郎は、当初、日本を象徴する色として「金色」を考えており、彼は「車体を金色に塗れ、できれば金箔を貼れ」と指示し、実際に初期の実験車両には金色が塗られたことも。
Image:Honda
この逸話は、ナショナルカラーが単なるルールや義務ではなく、国や企業の誇り、そして創業者の強烈なビジョンを体現するものであったことを物語っています。
しかしながら最終的に、「金色」はさまざまな理由から実用化には至りませんでしたが(一説には、当時アフリカがゴールドをナショナルカラーに指定していたからだと言われる)、このエピソードは、色がどれほど情熱的で個人的な意味を持っていたかを示す好例です。※なお、純白ではなくアイボリーが下地に選ばれたのも、ドイツとの混同を避けるためだという説がある
そしてもし、当時ホンダが日本のナショナルカラーとしてゴールドを選択できていたならば、現代の「タイプR」は「ホワイトにレッド」ではなく、「ゴールド」であったのかもしれません。
主要国のナショナルカラーリスト
| 国名 | 初期のカラー | 現在の代表的なカラー | 象徴的なメーカー/チーム | 補足・備考 |
| イタリア | 黒 | 赤 | フェラーリ、アルファロメオ | 「ロッソ・コルサ」と呼ばれる。 |
| ドイツ | 白 | 銀(または白) | メルセデス・ベンツ、アウディ | 「シルバーアロー」の伝説を持つ。 |
| イギリス | 緑 | 緑 | アストンマーティン、ベントレー、ロータス | 「ブリティッシュ・レーシング・グリーン」として定着。 |
| フランス | 青 | 青 | アルピーヌ、リジェ、プロスト | 「フレンチ・ブルー」の伝統を継承。 |
| 日本 | 白地に赤丸 | 白地に赤丸 | ホンダ、トヨタ | ドイツの白と被らないよう工夫された。 |
| アメリカ | 赤 | 青地に白ストライプ | イーグル、キャノンデール | 時代によって赤や白など変遷している。 |
こうやって歴史を振り返ると、モータースポーツの黎明期、ナショナルカラーはゴードン・ベネット・カップという特定のイベントのための「国籍識別」という行政的なルールであったことがわかりますが、しかし、ドイツの「白から銀への変更」のように、ルール違反を回避するための実用的な判断が、新たなアイデンティティとして定着したことも。
この成功は、色が単なる識別記号ではなく、勝利の物語や企業の誇りと結びつく「ブランド」となりうることを示唆しています。
その結果、ルールが撤廃された後も、これらの色は「伝統」として生き続け、現代のモータースポーツへと受け継がれているわけですね。
第2章:変革の時代―ナショナルカラーからスポンサーカラーへ
2.1. 商業主義の波:モータースポーツの近代化
1960年代後半、モータースポーツ、特にF1は大きな転換点を迎えます。
それまでの「金持ちの道楽」や「自動車メーカーの広報活動」という枠を超え、巨大な商業イベントへと変貌を遂げ始めており、この背景には、技術開発競争の激化と、それに伴う開発コストの爆発的な増加があったからだとされています。
モータースポーツに参戦する各チームはマシンの開発資金を捻出するため、外部からの大規模な投資を必要とするようになり、いわゆる「スポンサー」によってマシンが彩られる時代が到来したのがこのタイミング。
Image:Lotus
2.2. ロータスの決断:カラーリングのパラダイムシフト
この商業主義の波を象徴する出来事が伝説的なイギリスのチーム、ロータスの決断であったといい、当時ロータスは英国の伝統に従って車体に「ブリティッシュ・レーシング・グリーン」をまとってレースを走っています。
しかし、ロータスは資金確保のため、大胆な一歩を踏み出すことになり、彼らはナショナルカラーを捨て、タバコブランド「ゴールドリーフ」の赤と金色、そしてその後「ジョン・プレイヤー・スペシャル(JPS)」の黒と金色へと、車体色を劇的に変更することに 。
Image:Lotus
この出来事は、レースカーのカラーリングが「国の誇り」を示すものから、「スポンサーの広告塔」へと役割を完全にシフトさせた歴史的な転換点であったと記録され、JPSのブラックと・ゴールドのカラーリングは、ロータスそのもののブランドイメージとして深く定着し、スポンサーカラーがナショナルカラーを上回るアイデンティティとなりうることを証明するひとつの事実。
これにより、F1は「走る広告塔」としての側面を強め、レースカーのカラーリングは、スポンサー企業のブランド戦略を反映する重要な要素となる時代を迎えます 。
Image:Lotus
-

-
英国伝統の自動車メーカー、ロータスの誕生から現代に至るまでの歴史を考察。コーリン・チャップマンの残した功績はあまりに大きく、しかしその天才性に依存しすぎた悲運とは
| 「ロータス」は創業者であるコーリン・チャップマンの画期的な思想によってその名を知られるように | とくに「軽量」「ハンドリング」はそのブランドの”核”である 自動車の世界において「ロータス」という ...
続きを見る
第3章:現代のレーシングカラー事情と今後の展望
3.1. 最新のトレンド:つや消し塗装の秘密
現代のレーシングカーのカラーリングは、もはや美観や広告のためだけではなく、例えば多くのF1マシンが採用している「つや消し塗装」は、技術的な選択の結果です。
光沢のないマットな塗装は、通常のメタリック塗装に比べて塗料の層を薄くできるため、わずか数グラムとはいえ、車体の軽量化に貢献します。
モータースポーツの頂点では、コンマ1秒を削り出すためにあらゆる手段が講じられるため、これも重要な要素となっているわけですね。
一方で、映像や写真を通じてレースの魅力を伝えるカメラマンや解説者からは、「(以前の)艶ありの方が光を反射して、マシンがキラキラと輝き、かっこよく見える」という声も聞かれ、この事実は、現代モータースポーツにおいて、美的な「アート」と機能的な「サイエンス」が、時には対立する関係にあることを示しています。
3.2. コーポレートカラーの時代とナショナルカラーの再解釈
現代のレーシングカーのカラーリングは、スポンサーやチームのコーポレートカラーが主軸となっています。※ただし、このコーポレートカラーもまた、ナショナルカラーに由来する場合がある
しかし、過去のナショナルカラーが完全に消え去ったわけではなく、フランスのチームであるアルピーヌが、車体にトリコロール(赤、白、青)を大胆にあしらい、アストンマーティンが伝統的なブリティッシュ・レーシング・グリーンをまとってF1やWEC(世界耐久選手権)参戦しているように、旧ナショナルカラーの要素は、そのチームの「伝統」や「レガシー」として再解釈され、現代のデザインに巧みに取り入れられているという事実も。
Image:Astonmartin
これは、モータースポーツが、単なる技術競争や商業活動だけでなく、その歴史と文化を大切にするスポーツへと成熟したことを示していて、ナショナルカラーは義務ではなく、誇り高き過去を現代に伝える象徴として、その存在感を放ち続けているのだとも解釈することが可能です。
まとめ:色に込められた誇りと未来
自動車レースにおけるナショナルカラーは、ゴードン・ベネット・カップの時代から、スポンサーカラーの台頭、そして現代の技術トレンドに至るまで、その役割と意味を変え続けてきました。
ナショナルカラーの変遷
- 義務と識別: レース黎明期、国籍を識別するためのルール。
- 物語とブランド: 勝利の伝説や企業の誇りと結びつき、ブランドアイデンティティへと昇華。
- 商業と広告: スポンサーの広告塔としての役割が主流に。
- 伝統と機能: 現代においては、技術的な要請に応える一方で、伝統的な色を「レガシー」として再解釈。
Image:Alpine
レーシングカーの色は、その時代におけるモータースポーツのあり方(国威発揚、商業主義、技術革新)を映し出す鏡です。
ナショナルカラーは、義務としての役割を終えたものの、その精神と伝統は形を変えながら現代のモータースポーツに生き続けており、これからも、レースカーのカラーリングは、時代の変化を映し出し、新たな物語を紡いでいくこととなりそうですね。
あわせて読みたい、関連投稿
-

-
マクラーレンの歴史:レースと革新が織りなす究極のパフォーマンスへ、ニュージーランドの若き才能が蒔いた種が世界のモータースポーツの頂点に
| 多くの有名なスポーツカーメーカーは「創業者一族」の手を離れている | マクラーレンもまた「第三者の手に渡りつつ」しかしそのDNAを失っていない さて、歴史あるスポーツカーメーカーというとロータス、 ...
続きを見る