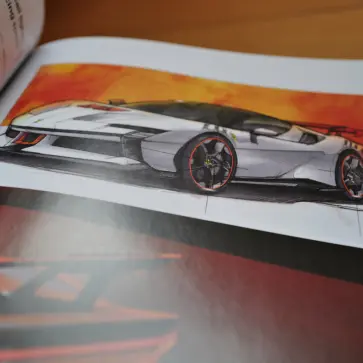| 日本は何かと「やる気」という不確定要素に評価が引っ張られがちである |
そして真の意味での「コミュニケーション」が理解されていない
さて、最近良く考えるのが「日本の管理職のあり方」。
海外で仕事をしているとつくづく日本の管理職が「特殊」だと感じることがあり、それは日本だと管理職(マネージャー)のほとんどが「管理ではなくプレイをする”プレイングマネージャー”である」ということ。
今回はこれについての影響そしてあり方を考えてみたいと思います。
そもそもプレーヤーとマネージャーとは「違う立場」である
まず、ぼくの認識として前提にあるのは「プレーヤーとマネージャーとは別の立場にある」。
あるいは階級が異なると言っていいかもしれませんが、プレーヤーとマネージャーはそのポジションと役割が全く異なるため、この立場を兼任させるということはその管理職の認識を混乱させることになり、そのミッションに対する認識を希薄化させることにつながると考えています。
「プレーヤーとマネージャー」という立場につき、これらは相反するものではなく、ただ単に「全く異なる」のだとも考えていて、これは「女王蜂と働き蜂」のような関係であり、女王蜂が働き蜂のように考え、同じように動くと組織は混乱し、またその逆も然り。
よって、その会社におけるプレーヤーとマネージャーも同様であり、プレーヤーはプレーヤー、マネージャーはマネージャーとして考えて行動する必要があると捉えているわけですね。
プレーヤーとマネージャーとの視点はこう違う
なお、現代社会においては「若者の責任感が低い」「出世意欲がない」「自発性がない」「言われたことしかやらない」とよく言われますが、これはおそらくいつの時代でも一定層で見られた傾向であると考えられ、しかし統計上そのトレンドが強くなっていることは間違いなさそう。
そこでぼくの考えるマネージャーの役割ですが、「そういった、意識が低いと捉えられている人を鼓舞してモチベーションを高め、やる気を出させる」ことではなく、「言われたことしかやらない」人たちに、「言ったことだけをやらせる」ことだと思うわけですね。
上述のような「出世意欲が低い」、つまり現代でいう「静かな退職」という働き方を選んだ人々の意識を改革することは難しく、大変な老職がかかる割にリターンが小さく、かつ効果が持続しない方法です。
よって現代のマネージャーとしては「言われたことをキッチリさせる」ことに主眼を置くべきで、例えばぼくの考えるマネージャーの仕事の流れは以下の通り。
- マネージャーが会社から課せられたミッションをちゃんと理解する(売上、利益、生産性向上などなど)
- そのミッションを達成するためのタスクを洗い出す(まずはこれを行い、次にこの段階に進むなど)
- 自分の抱える組織のメンバーの性格な能力と傾向を把握し、そのタスクを適切な人間に割り当てる
- タスクを割り当てるに際し、その人間にはしっかりと「目的や意図、求める成果」を説明する
ボクの考える「仕事」とは
ぼくは常々、仕事とは「どれだけ大きなサイズの絵を描けるか」だと考えていて、例えばマネージャーが会社から何らかの指示を受けた場合、その指示を実行した結果(あるいは成果)を一枚の絵に例え、「こういった絵を、こういったサイズで描く」と考えるわけですね。
そしてまずは(そのサイズの)白紙を「パズルのように分解し」、そして分解したピースを組織の各メンバーに与え、そのメンバーそれぞれにピースに絵を描かせ、そのピースを組み上げたときに「予想通りの絵になる」ようにすることが「マネージャーの仕事」だと認識しています。
よってマネージャーが「メンバー個々と同じ”ピース”を見ていては完成状態を把握できず(木を見て森を見ない状態)、よってマネージャーは完成状態をイメージし、個々のメンバーがピースを適切に仕上げるように「仕事を割り振り」、その仕事の進捗を管理することによってのみミッションをクリアできると考えているわけですね。
よって、できるかどうかわからない人間をおだて、鼓舞し、松岡修造のように「一緒に頑張ろう!」「やればできる!」といって聞かせるのは会社のマネージャーとして期待される仕事内容ではなく(松岡修造を否定しているわけではなく、ある場面では松岡修造的な行動が求められるが、この場合はそうではない)、より確実性を期し「確実に、それをできるメンバーに仕事を割り当て、その仕事をきっちり行わせる」という文字通りの”管理”業務が管理者つまりマネージャーに求められるもので、自らプレイすること、そして「モチベーション」という不確実な要素に賭けることは管理者として失格なんじゃないかとも考えています。
そして「ぼくの考えるマネージャー」に求められるのは、「コーチ」「リーダー」ではなく、現状分析能力に長け、ミッションを理解し、そのミッションを達成するためには何が必要なのかを理解できる人物で、冷静かつ客観的に「誰に何を行わせればどういった結果を得られるか」が理解できており、そのための指示を適切に自身が管理する人員に対して述べることができる「説明能力」を持つ人物というわけですね。※これが正しいコミュニケーションだとも考えており、部下を引き連れて飲み歩くことがコミュニケーションではない
さらに言えば、マネージャーの仕事を理解せず、マネージャーに「プレイ」させる会社にも問題があると考えており、マネージャーには「マネージャーとしての」結果を求め、マネージャーとしての評価を行う必要があるのかもしれません。
そして前出の「静かな退職」「言われたことしかやらない」につき、ぼくはこれに対して否定的な見解をもっておらず、むしろ「言われたことができるのは一つの才能」だとも認識していて、言われたことしかやらない人だけを集め、それらの人々に適切に指示ができる管理者がいる組織こそが「現代最強」なんじゃないかとも捉えています。
むしろ、この不確実性溢れる現代において、「自らの理想を掲げる」”熱い”、そして一見してやる気に溢れるメンバーは組織にとって危険分子となりうる要素をはらんでおり、こういった世の中だからこそ、「仕事は仕事」として自身の生活と切り分けることができる人物のほうが企業にとって有用なのかもしれません。
そしてそういった、一見して「やる気のない人々」こそが今後の起業の成長に欠かせない人物であり、そういった人たちの能力や適性を把握し、最適な業務を割り振りでき、管理できるマネージャーこそがいま企業に求められる管理者かのかもしれません。
あわせて読みたい、関連投稿
-

-
なぜ日本の会社では「コミュニケーションが重要」「人付き合いが大事」とされるのか?ボクが「それがビジネスの速度を遅くする原因であり、幻想でしかない」と思うワケ
| 日本の社会は未だに「やればできる」「話せばわかる」という根性論に支配されている | それが結果的にスピードを遅くし、国際競争力を貶めている さて、ビジネスを進めるうえでよく(商談先から)言われるの ...
続きを見る
-

-
ボクは80%までしか目指さない。その理由は「0から80%まで仕上げるのは容易だが、80%から100%にまで仕上げるのは容易ではないから」
| そもそも100%はこの世に存在せず、その基準は人によって変わるのだから、それを追求してもムダである | であれば「80%」にとどめておき、100%を目指すための労力を別のことにかけたほうがずっとい ...
続きを見る
-

-
「前にいる遅いクルマを抜いたとしても、その先が渋滞で詰まっていれば意味がない」とは言うけれど
| ボクにとって前のクルマを抜くということは、自分で自分の人生を切り開くこと、自由を得ることを意味している | たとえ結果が同じだとしても、そこに至るまでには信念を貫くべきである さて、ときどき論じら ...
続きを見る