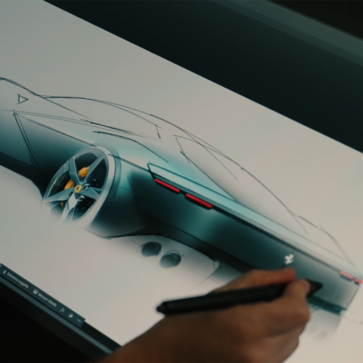| フェラーリの株価は今年に入って「最高値」を記録 |
フェラーリの成長は過去のブランド価値に依存するものではなく、未来を作り出そうと据えう人々によってもたらされている
しかも「トランプ関税」の懸念がある中での出来事である
フェラーリは単なる自動車メーカーの枠を超え、比類なきパフォーマンス、デザイン、そして限定性によって「ラグジュアリーブランド」としての確固たる地位を築いています。
そのブランド価値は、製品の価格設定だけでなく、株式市場での評価にも明確に表れており、投資家はフェラーリを単なる製造業ではなく、唯一無二の高級品(ラグジュアリー)企業として捉えていて、実際に今年に入って株価が過去最高値を記録するといった傾向も。
ここでフェラーリの業績、そして株価を振り返ってみたいと思います。
はじめに:跳ね馬の軌跡を辿る
フェラーリの企業価値は、従来の自動車産業の指標である販売台数や利益といった財務数値だけでなく、ブランドの希少性、歴史、そして顧客が抱く感情的価値に大きく依存していることが市場での高い評価に表れています。
例えば、フェラーリの株式が「ラグジュアリー企業同様に」取引されるのは、限定生産と高い再販価値がその「比類なきプレステージ」を維持しているためで、このような無形資産が市場における(自動車業界として例を見ない)高い評価倍率と持続的な株価上昇の直接的な要因となっているから。
これは、投資家が将来の成長性だけでなく、ブランドが提供する独特の体験やステータスに価値を見出していることを明確に示しています。
フェラーリの成功は、製品そのものの卓越した性能だけでなく、ブランドストーリー、顧客体験、そして意図的な希少性創出がいかに企業価値を高めるかの好例であり、他の”高級ブランドや、単なる製品販売から「体験」や「ステータス」販売へとビジネスモデルを移行しようとする企業”にとって重要なベンチマークとなり得ると考えられており、実際に「フェラーリのビジネスモデル」を真似るブランドが複数登場していることでもその影響力がわかろうというものですね。
そしてフェラーリは「(エルメスのように)代替品がない」ことでも知られており、ポルシェがIPOを行う際、自身をして「フェラーリと同等の市場価値があり、フェラーリを超える時価総額を達成する」と主張した際、多くのアナリストが「フェラーリは唯一無二の存在であるが、ポルシェはそうではなく、社会の構造変化やライバルの台頭によって価値を失う可能性がある」と指摘したこと、そして実際にそれが現実となったことからもフェラーリの”独自の価値”がわかるかもしれません。
第1章:フェラーリ株価の変遷と市場評価
IPOから現在までの株価推移
フェラーリは2015年10月21日にニューヨーク証券取引所(NYSE)に「RACE」のティッカーシンボルで上場し、IPO価格は1株あたり52ドルを記録しています。
その後、2016年1月4日にはミラノ証券取引所(MTA、現ユーロネクスト・ミラノ)にも上場し、1株あたり43ユーロで取引を開始しています 。
IPOから約9年半後の2025年7月162日時点で株価は約505ドルに達しており、IPO価格から約9.7倍以上という驚異的な上昇を記録しています。これは、100万円の投資が970万円以上となった計算に相当し(1000万円だと9700万円)、52週高値は509.13ドルという数字に。
IPO価格から約10年で株価が急騰したことは、単なる市場の成長を超えた、フェラーリに対する投資家の強い信頼と「プレミアム評価」を示していて、「500ドル、P/E(株価収益率)45倍以上」で取引されるという高い評価は、一般的な自動車メーカーの評価水準をはるかに上回るもの 。
これは、フェラーリが自動車産業の枠を超え、ラグジュアリーブランドとしての稀少性や将来の成長性、そして安定した収益性(後述の業績部分で説明)が評価されている証拠でもあり、企業が持つ「ブランド力」と「限定的な供給戦略」が、市場における「高い評価倍率」と「持続的な株価上昇」の直接的な原因となっています。
これは、投資家が単に財務的な数字だけでなく、ブランドが提供する無形資産に大きな価値を見出していることを示していることにほかならず、フェラーリの株価推移は、投資家が単なる財務諸表上の数字だけでなく、企業の「ブランドストーリー」や「市場でのポジショニング」を深く評価していることを示唆していますが、特にラグジュアリーセクターにおいては、希少性とブランドヘリテージが強力な経済的モート(堀)となり、株価の安定性と成長性を支える重要な要素となることが知られています。
主要な株価指標と市場の反応
2025年7月時点でのフェラーリ株は、2024年予想調整後EBITDAの30倍以上で取引されており、これは平均よりも高い評価であるものの、その堅固なブランド力とビジネスモデルがこのプレミアムな評価を正当化している(つまり割高ではない)と分析されています 。
2025年5月6日に発表された2025年第1四半期決算では、アナリスト予想を上回る好決算を記録し、これによって株価は年初来で9.8%上昇し、S&P500の-3.9%下落を大きくアウトパフォームすることに 。
これは、市場がフェラーリの堅調な業績を高く評価していることを示していて、テクニカル分析では、一時的な後退(ガイダンスや関税への懸念によるものとされる)はあるものの、株価は520ドルから540ドルへの潜在的な上昇余地があるとの見方が示されています 。
こういった株式の動き、そして分析は”絶対的な好業績”だけでなく、「市場の期待値」を上回ることが株価にポジティブな影響を与えるという市場心理の基本的な側面を浮き彫りにしていますが、テクニカル分析が、ガイダンスや関税の懸念を「”一時的な”後退(永続する脅威になるものではない)」と見なしているのも、根本的な企業価値への信頼があるためなのかもしれません 。
企業が設定する「ガイダンス」と、それを「上回る実績」が、投資家の「信頼」と「株価のポジティブな反応」を直接的に生み出すと考えられ、これは単に数字を出すだけでなく、市場との効果的なコミュニケーションと期待値管理が株価形成において極めて重要であることを示唆していますが、フェラーリの場合、限定生産と高価格戦略が、予測可能性の高い高収益を可能にし、それが投資家の期待値管理を容易にするとともに(つまり部外者でもその戦略と効果を理解しやすい)、企業が市場の期待を継続的に上回る能力は、その企業が持つ競争優位性、効率的な経営、そして将来の成長機会を強く示唆しています。
COVID-19パンデミックの影響と回復力
2020年第2四半期は、COVID-19パンデミックの影響を大きく受け、出荷台数は前年比48%減の1,389台、純売上高は42%減の5億7,100万ユーロ、調整後EBITDAは90.3%減の1億2,400万ユーロと、大幅な業績悪化を経験しており、特に、生産停止やディーラー閉鎖が影響してV8モデルは49.4%減、V12モデルは42.9%減。
地域別でもEMEAが40.9%減、アメリカが52.6%減と軒並み落ち込んでいますが、これはフェラーリの需要が減ったというわけではなく、「単に生産ができなかったから」。
実際のところ、フェラーリは「100%が受注生産」であり、キャンセルは0件であったとも報じられているため、パンデミックによって「会社が傾く」ことはなく、しかしその一方、「在庫車を抱える」ビジネスモデルを採用していたアストンマーティンとマクラーレンの経営が危機に陥ったことは記憶に新しいところかもしれません(これらは経営母体が変わるほどの影響を受けている)。
これを証明するかのように、同四半期にはF8スパイダーや812 GTSの初期納車が開始され、2020年通期ガイダンスも下方修正されたものの「当初の予測範囲内」に収まる見込みだとされています。
2020年当時の世界的な自動車需要は15%減少し、しかし2021年には9-13%の回復が予測され、2023年には正常な需要レベルに戻ると見込まれていましたが(事実そうなった)、フェラーリはこの回復期において「業界平均を遥かに上回る記録的な売上高と堅調な収益性」を達成し、むしろガイダンスを引き上げることに。
つまるところ、2020年第2四半期のパンデミックによるフェラーリの業績への壊滅的な影響は明らかですが 、一般的な自動車産業がパンデミックから回復する過程で直面した課題(半導体不足など)にもかかわらず、フェラーリのような超高級ブランドは、その顧客層の富裕さとブランドへの強いロイヤルティにより、需要の落ち込みからの回復が早く、より強力であったことが示されています 。
これは、「限定生産」と「富裕層顧客基盤」というフェラーリのビジネスモデルの特性が、「外部ショック(パンデミック)に対する需要の非弾力性」と「迅速な回復」を可能にしていることを示唆するとともに、景気変動の影響を受けにくいラグジュアリーセクターの特性を強く示しており、経済危機時においても、超富裕層の消費行動は比較的安定していること、特にステータスシンボルとしての高級品への需要が底堅い傾向にあることの証明です。
フェラーリの回復力は、このような市場特性を最大限に活用したビジネスモデルの強靭さを示しており、他の高級ブランドにとっても重要な教訓、あるいは「手本」となっているわけですね。
第2章:堅調な業績推移:収益性と利益構造
年間売上高と利益の成長
フェラーリは2015年のIPO以来、売上高と利益を着実に成長させており、2015年から2023年までの売上高の年平均成長率(CAGR)はなんと10% 。
特に2024年は、純売上高が66億7,700万ユーロに達し、前年比11.8%増を記録しましたが、これは、同社が「販売台数よりも収益の質」を重視する戦略を成功させていることを裏付けています 。
過去の推移を見ると、2023年の売上高は59億7,000万ユーロ、2022年は50億9,500万ユーロ、2021年は42億7,100万ユーロ、2020年は34億6,000万ユーロと、一貫した成長を示していて、純利益も同様に増加傾向にあり、2024年には15億2,600万ユーロに達することに。
主要財務指標の分析:EBITDA、純利益、EPS
調整後EBITDA(利払い前・税引前利益)は、2024年に25億5,500万ユーロ(マージン38.3%)に達し、2023年の22億7,900万ユーロ(マージン38.2%)からさらに改善。
この高いマージン率は、フェラーリの強力な価格決定力と効率的な経営を示していて、調整後営業利益(EBIT)も2024年に18億8,800万ユーロ(マージン28.3%)と堅調に推移、さらに株式希薄化後EPSは2024年に8.46ユーロを記録し、2023年の6.90ユーロから増加しています 。
これらの指標は、フェラーリが「販売台数よりも収益の質」を重視する戦略を成功させ、持続的に高い収益性を維持していることを明確に示していますが、2024年の調整後EBITDAマージンが38.3%という非常に高い水準を維持していることは、単に売上を伸ばすだけでなく、より高価なモデル(SF90XX、12チリンドリ、499Pモディフィカータなど)の販売比率を高め 、パーソナライゼーション(自動車およびスペアパーツの売上の19%以上を占める)を強化することで 、一台あたりの収益性を最大化する戦略が奏功していることを明確に示す例。
電動化モデルも「プレミアム価格設定と簡素化された機械システム」により高マージンに寄与すると具体的に述べられており 、この戦略の多角的な側面を浮き彫りにしています。
このように、「限定生産」と「高価格戦略」、そして「高付加価値モデルへの注力」がフェラーリの「高い収益性」と「持続的な利益成長」の直接的な原因となっていることが明らかで、これは一般的な自動車産業が直面するボリュームと価格競争(いわゆる”底辺の争い”)から一線を画す、フェラーリ独自の競争優位性を示しています。
フェラーリの財務戦略は、ラグジュアリーブランドがどのようにして市場の変動に左右されずに高収益を維持できるかを示す模範例でもあり、これは製品の希少性を維持し、顧客のカスタマイズ要求に応えることで単価あたりの利益を最大化するという、高級品ビジネスの核心を突いている端的なビジネスモデルということになりますね。
フェラーリ年間出荷台数と主要財務指標の推移 (2015-2024)
| 年 | 出荷台数 (単位) | 純売上高 (€M) | 調整後EBITDA (€M) | 調整後EBITDAマージン (%) | 調整後営業利益 (EBIT) (€M) | 調整後営業利益 (EBIT) マージン (%) | 純利益 (€M) | 希薄化後EPS (€) | |
| 2024 | 13,752 | 6,677 | 2,555 | 38.3% | 1,888 | 28.3% | 1,526 | 8.46 | |
| 2023 | 13,663 | 5,970 | 2,279 | 38.2% | 1,617 | 27.1% | 1,257 | 6.90 | |
| 2022 | 13,221 | 5,095 | 1,773 | 34.8% | 1,227 | 24.1% | 939 | 5.09 | |
| 2021 | 11,155 | 4,271 | 1,531 | 35.9% | 1,075 | 25.2% | 833 | 4.50 | |
| 2020 | 9,119 | 3,460 | 1,143 | 33.0% | 716 | 20.7% | 609 | 3.28 | |
| 2019 | 10,131 | 3,766 | 1,269 | 33.7% | 917 | 24.4% | 699 | 3.71 | |
| 2018 | 9,251 | 3,420 | 1,114 | 32.6% | 825 | 24.1% | 787 | 4.14 | |
| 2017 | 8,398 | 3,417 | 1,036 | 30.3% | 775 | 22.7% | 537 | 2.82 | |
| 2016 | 8,014 | 3,105 | 880 | 28.3% | 632 | 20.4% | 400 | 2.11 | |
| 2015 | 7,664 | 2,854 | 748 | 26.2% | 473 | 16.6% | 290 | 1.52 | |
このテーブルは、フェラーリがIPOを行った2015年からの約10年間の財務と出荷台数の変遷を一目で把握できるようにしたもので、出荷台数の緩やかな増加(ブランドの限定性維持)と、純売上高・利益のより急峻な増加(高価格化、高付加価値化)の乖離を明確にし、「収益の質」戦略の成功を裏付けます(販売台数よりも、売上高と利益の増加のほうが著しく高い)。
また、マージン率の推移から、収益構造の改善や効率性の向上も読み取ることができますが、フェラーリのビジネスモデルの健全性と持続可能性を評価するための最も重要なデータセットであり、ラグジュアリーブランドがどのようにして成長と限定性を両立させているかを理解する上で不可欠な数字であるとも考えています。
2025年第1四半期決算のハイライトと今後の見通し
2025年第1四半期は全ての主要財務指標で二桁成長を達成し、特に純売上高は前年比13%増の17億9,100万ユーロ、出荷台数は1%増の3,593台へ。
ここでは収益性が際立っており、EBITDAは15%増の6億9,300万ユーロ(マージン38.7%)、EBITは23%増の5億4,200万ユーロ(マージン30.3%)を記録したうえ、純利益は17%増の4億1,200万ユーロ、希薄化後EPSは18%増の2.30ユーロと堅調な利益成長を示しています 。
フリーキャッシュフローは6億2,000万ユーロと非常に堅調で、純工業負債は2024年末の1億8,000万ユーロから4,900万ユーロに大幅に減少し、「これは、企業の財務体質がさらに強化されていることを示しています。
事業部門別では、自動車およびスペアパーツの売上が15億3,600万ユーロ(前年比11%増)、スポンサーシップ、商業、ブランド収入が1億9,100万ユーロ(32%増)と好調に推移。※特にHPとの新たなタイトルスポンサーシップが大きく貢献
地域別ではEMEAが1,701台(8%増)、アメリカが1,022台(3%増)と好調だった一方、中国およびその他のAPAC地域は税制や”戦略的配分”により減少傾向。※フェラーリは中国での販売、とくにスポーツモデルの供給を絞っていると言われる
製品ミックスはICEモデル51%、ハイブリッドモデル49%とほぼ均等であり、ローマ・スパイダー、296 GTS、SF90 XX、プロサングエなどが成長を牽引しています。
2025年通期ガイダンスは、純売上高70億ユーロ超、調整後EBITDA26億8,000万ユーロ以上(マージン38.3%以上)、工業フリーキャッシュフロー12億ユーロ以上となりますが、米国にてトランプ政権が導入する関税がEBITマージンに影響を与える可能性を認識しつつも、価格調整などの緩和策を講じていると説明されています 。※関税にかかわらず、CEOのベネデット・ヴィーニャ氏は、12チリンドリとプロサングエへの強い需要が2026年まで続くと強調している
そして特筆すべきは、2025年第1四半期において出荷台数がわずか1%増に留まったにもかかわらず、純売上高が13%増、EBITDAが15%増と、利益率が大幅に向上したこと。
これはフェラーリが単に台数を増やすのではなく、より高価なモデル(SF90XX、12チリンドリ、499Pモディフィカータなど)の販売比率を高め、パーソナライゼーションを強化することで”一台あたりの収益性を最大化する”戦略が奏功していることを明確に示しています 。※よって、販売台数が伸びていない=フェラーリの需要が減ったというのはあまりに短絡的な見解である
さらには高マージンな電動化モデルの販売比率増加もこれを補強する形となり、「限定的な生産量」を維持しつつ「製品ミックスの最適化」と「パーソナライゼーションの強化」を行うことにより、フェラーリは「高い収益性」と「キャッシュフローの創出」を実現しているわけですね。
これは、ラグジュアリーブランドが成長を追求しつつも、ブランドの希少性を希薄化させないための精緻なバランス戦略であり、フェラーリの2025年第1四半期の結果は、量産を追求する自動車産業とは異なる、高級品市場における成長モデルの顕著な成功例だと見られており、供給を厳しく管理し、顧客の個別ニーズに応えることで、プレミアム価格を維持し、高い利益率を確保するという戦略は、他の高級ブランドにも応用可能な普遍的な教訓を提供しています。
フェラーリ2025年第1四半期主要財務ハイライト
| 指標 | 金額 | |
| 純売上高 | €1,791 million (+13% YoY) | |
| 出荷台数 | 3,593 units (+1% YoY) | |
| EBITDA | €693 million (+15% YoY) | |
| EBITDAマージン | 38.7% | |
| EBIT | €542 million (+23% YoY) | |
| EBITマージン | 30.3% | |
| 純利益 | €412 million (+17% YoY) | |
| 希薄化後EPS | €2.30 (+18% YoY) | |
| 工業フリーキャッシュフロー | €620 million | |
| 純工業負債 | €49 million (2024年末の€180Mから減少) | |
最新の四半期決算は、企業の直近の健全性と将来の方向性を示す最もタイムリーな指標であり、フェラーリが直面するマクロ経済的課題(米国関税など)にもかかわらず、いかに堅調なパフォーマンスを維持しているかを具体的に見ることができます。
出荷台数の微増と売上・利益の二桁成長の対比から、「質を重視する戦略」が短期的に成功していることを裏付けており、工業フリーキャッシュフローの強さや純工業負債の急減は、企業の財務体質の改善と将来の投資余力を示唆していると考えられますが、ぼくら投資家にとって、フェラーリが短期的な市場の変動に強く、長期的な成長戦略(特に電動化)を着実に実行するための財務基盤が確立されていることを確認できる重要な情報源でもありますね(これらの数字はフェラーリが公式に発表しているもので、オフィシャルサイトから拾うことができる)。
第3章:販売台数の動向:戦略的成長と市場の変化
年間出荷台数の推移と成長要因
フェラーリの年間出荷台数は、2015年の7,664台から2023年には13,663台へと着実に増加し「ほぼ倍増」。
2024年には世界全体で13,752台を納車し、2023年から0.7%の微増を記録していますが、この「わずかな増加」は、上述の通りにフェラーリが販売台数よりも収益の質を重視する戦略を継続していることを強く示唆しています 。
売上成長の主要因は、アメリカ(販売台数8%増)とヨーロッパ(5.0%増)の強い需要であり、中国の減少(38%減)を効果的に相殺し、ハイブリッド技術と限定性がブランドのプレミアム価格と魅力を維持する重要な要因となっていと説明されています。
地域別販売動向と主要市場の分析
2023年から2024年にかけ、主要6カ国(米国、日本、ドイツ、英国、イタリア、フランス)の販売台数は合計で8.7%増加。
米国は2024年に3,527台(+12.9%)で引き続き最大の市場であり、プロサングエやSF XX系などの新モデルが販売を牽引し、ドイツは1,827台(+11%)で日本を抜き第2位の市場となりましたが(そう、日本はこれまで2位であったが3位に転落した)、2024年下半期には登録台数が減少する傾向も 。
イタリアは744台(+14%)と堅調な成長を見せ、国内市場での根強い人気を示す一方、英国は940台(-4.4%)と減少傾向にあり、地元ブランド(マクラーレンやアストンマーティン)との競争が要因として挙げられています 。
フェラーリ地域別販売台数と成長率 (2023-2024)
| 国名 | 2023年販売台数 (単位) | 2024年販売台数 (単位) | 成長率 (%) | |
| 米国 | 3,124 | 3,527 | +12.9% | |
| 日本 | 1,395 | 1,445 | +3.5% | |
| ドイツ | 1,646 | 1,827 | +11% | |
| 英国 | 984 | 940 | -4.4% | |
| イタリア | 652 | 744 | +14% | |
| フランス | 319 | 347 | +8.7% | |
| 主要6カ国合計 | 7,801 | 8,483 | +8.7% | |
| 中国 (全体) | - | - | -38% (2024年) | |
中国市場は2024年に38%の大幅な減少を経験したものの、これは税制や戦略的配分によるものと説明されていますが、2024年および2025年第1四半期において中国市場での販売が大幅に減少したこと(38%減)は、フェラーリが単一市場への過度な依存を避け、地域間のバランスを取る戦略の重要性を浮き彫りにしています 。
米国やヨーロッパでの成長が全体を牽引していることから、特定の市場での外部要因(税制、地政学など)が販売台数に直接影響を与える可能性があることが示されており、フェラーリの「地域分散」と「戦略的配分」は、このようなリスクを軽減し、全体としての「安定した成長」を可能にするための重要な要素です。※グッチやバーバリーなどのハイブランドが「中国に依存し」、その反動で販売を大きく落としたことからも市場依存の危険性を理解できる
これは、高級ブランドがグローバル市場で持続的な成長を達成するために、地域ごとの市場特性を理解し、柔軟な戦略を適用することの重要性を示しています。
プロサングエの成功と顧客層の変化
フェラーリ初のSUVであるプロサングエは、2022年9月の発売以来、急速にトップセラーモデルの一つとなり、2024年1月から8月にかけては296GTB/GTSとローマ/ローマ・スパイダーに次ぐ第3位の販売台数を記録。
プロサングエはその高い価格設定が示すように 、一台あたりの収益を大幅に増加させ、フェラーリ全体の売上とEBITマージン向上に貢献しています。
さらにこのプロサングエの導入はフェラーリの顧客層にも変化をもたらしていて、CEOのベネデット・ヴィーニャ氏によると、2024年には新規顧客の40%以上が40歳未満であり、2023年の30%から大幅に増加。
これはまさに「プロサングエ効果」によるもので、プロサングエは、これまでフェラーリに興味を示さなかった顧客層からの関心を集めたとされており、その多用途性と実用性が、より若い富裕層のニーズに応えているものと考えられます 。
しかし、フェラーリは依然として「ゲートキーピング」戦略を維持しており、2024年の新規販売の81%は既存顧客向けにのみ開放され、その半数近くがすでに複数のフェラーリを所有している層。
これは、プロサングエが新しい顧客層を引きつけつつも、ブランドの排他性と既存顧客へのロイヤルティを維持していることを示しており、プロサングエの成功は、フェラーリがブランドの核となる価値を損なうことなく、市場のトレンド(SUV需要)に適応し、新たな収益源と顧客層を獲得できる能力があることを示していますが、この戦略は、ブランドの伝統と革新のバランスを保ちつつ、持続的な成長を追求するフェラーリの姿勢を明確にしています(新規顧客比率が増えるとブランドの戦略に影響を与え、既存顧客をベースとしたビジネスモデルにも影響を与えるので、一気に顧客を入れ替えることは避けねばならない)。
電動化モデルの導入と販売戦略
電動化について触れておくと、フェラーリは電動化への移行を加速しており、2025年後半までに販売台数の60%を完全電気自動車(BEV)とプラグインハイブリッド車(PHEV)で構成することを目指しています 。
2025年第1四半期には、ハイブリッドモデルがすでに納車台数の約49%を占め、収益性向上に貢献していますが、ハイブリッドモデルは、そのプレミアムな価格設定と簡素化された機械システムにより、高いマージンに寄与するという説明も(つまりフェラーリにとってのハイブリッドは”儲かる製品”である) 。
なお、フェラーリ初の完全電気自動車「エレットリカ(正式名称は不明)」は、2025年10月にその「技術的な核」が公開され、2026年春に車両全体がデビュー、2026年10月には顧客への納車が開始される予定となりますが、価格は50万ユーロ(約8600万円)を超えると予想されており、テスラ モデルSの最上位モデルに匹敵する加速性能、そしてフェラーリの音響的アイデンティティを保つための合成V12エンジンサウンドシステムが特徴とされています 。
ただ、いかに「テスラ並みの加速」を誇るといえど、フェラーリの電動化戦略は、テスラの市場シェアを追うのではなく、電動化時代における「排他性」を再定義することに焦点を当てているのはこれまで通り 。
限定的な生産量とプレミアム価格設定により、価格競争からブランドを守り、高いマージンを維持することを目指していて、これは、ブランドの伝統を維持しつつ、技術革新を取り入れ、新たな市場ニーズに応えるというフェラーリの戦略的アプローチを示しています。
第4章:未来への展望:電動化とブランドの進化
電動化戦略の進捗と「E-Building」の役割
フェラーリの電動化への転換は、単なる野心ではなく、具体的な進捗を伴っています。
上述べた通り、2025年後半までに、フェラーリのラインナップの約60%が完全電気自動車とハイブリッド車で構成されるという目標が掲げられていますが、この目標達成に向け、2024年6月にはマラネロに新しい「E-Building」が竣工したのは既報の通り。
このE-Buildingは、単なる工場拡張ではなく、フェラーリ初の完全電気自動車「エレットリカ」のほか、SF90シリーズや296GTB/296GTSなどのハイブリッドモデルの製造も担う、技術的・生態学的な革命を象徴する施設です 。
3,000枚の太陽光発電パネルによる1.3MWのクリーンエネルギー生成、雨水リサイクルシステム、高度なロボット技術などを導入し、環境負荷を最小限に抑えながら、フェラーリが求める性能と品質基準を維持するように設計され、最大では年間20,000台の生産能力を持つものの、フェラーリは排他性を重視し、単一モデルが販売の20%を超えることはないという方針を維持するとされ、つまり「いかに生産能力に余剰があろうとも、今まで通り、供給が厳しく制限される」。
参考までに、フェラーリは「2027年までの生産枠が埋まっている」とコメントしているものの、それは「工場のキャパシティの限界に達している」という意味ではなく、「フェラーリが決めた、限定された生産台数を維持しつつ」というただし書きがつくと捉える必要がありそうです。
なお、この生産施設の柔軟性は、ガソリン車、ハイブリッド車、電気自動車の生産を迅速に切り替えることを可能にし(つまりどのような変化にも対応できる。「E」と名がつくが、これはエレクトリックを意味するものではない)、将来の技術的課題への適応力も高めていますが、この分野への投資は、フェラーリが持続可能なイノベーションを追求し、2030年までにカーボンニュートラルを達成するというコミットメントとも一致しています 。
投資家からの評価と潜在的なリスク
投資家はフェラーリが電動化時代においてもそのブランド力を維持し、高マージンを確保できると確信しており、実際に2025年第1四半期のEBITマージンが30.3%に達し、前年から大きく改善したことは、電動化モデルの比率増加が貢献したと認識されていて、これはフェラーリが電動化を収益性向上のための戦略的手段と位置付けていることを示しています。
しかしこれと同時にリスクが存在することも指摘され、米国にて導入される新たな関税は、2025年のEBITマージンを減少させる可能性があり、価格調整などの緩和策が講じられています(そして、それだけでは調整できないであろう)。
また、高性能EVに対する需要の過大評価や、バッテリー重量、航続距離の不安といった技術的課題も残されており、サプライチェーンの変動やバッテリー材料費の高騰もマージンを圧迫する可能性が指摘されているという現状も。
それでも、フェラーリの「限定生産」と「プレミアム価格設定」は、他社とのコモディティ化競争からブランドを守る強力な盾として機能することは間違いなく、エレットリカの50万ユーロ超という価格設定は”極めて高いマージン”を保証すると見られています 。
フェラーリは、内燃機関(ICE)モデルによる安定したキャッシュフローを維持しつつ、EV需要を慎重に探るという段階的なアプローチをとることで、大量生産EVに全賭けする企業が直面するような実存的リスクを軽減していますが、この「両方の良いとこ取り」戦略により、フェラーリはセクター全体の混乱の中で、より安全なラグジュアリーブランドとしての投資先として位置付けられているわけですね。
まとめ:ラグジュアリーブランドとしてのフェラーリの持続的な魅力
フェラーリは、IPO以来、株価、業績、販売台数の全てにおいて目覚ましい成長を遂げてきましたが、その成功の根底には、単なる自動車メーカーではなく、比類なき「ラグジュアリーブランド」としての地位を確立し、維持してきた戦略があります。
株価はIPOから約10年で約9.7倍に上昇し、市場はフェラーリを高いP/E比率で評価していて、これは、限定生産と強力なブランドヘリテージがもたらす希少性と安定した収益性への信頼の表れでもあり、COVID-19パンデミックのような外部ショックに対しても、富裕層顧客層の需要の非弾力性と迅速な回復力を見せつけることに。
業績面では、「販売台数よりも収益の質」を重視する戦略が奏功し、高マージンを維持しながら売上と利益を着実に伸ばしており、特に高価なモデルやパーソナライゼーションの強化が収益性向上に貢献し、2025年第1四半期も出荷台数の微増に対して売上と利益の二桁成長を達成しています。
販売台数においては、プロサングエの成功が新たな顧客層、特に若年層を引きつけつつも、既存顧客との強固な関係を維持しており、地域別では中国市場の減速が見られるものの、米国やヨーロッパでの力強い需要が全体を牽引し、市場の多様化がリスクを分散しています。
未来に向けて、フェラーリは電動化戦略を加速しており、マラネロのE-Buildingはまさにその象徴。
初の完全電気自動車「エレットリカ」の導入は、ブランドの核となる価値を損なうことなく、電動化時代における「排他性」を再定義する試みでもあり、投資家はこの段階的な電動化アプローチと、ブランドが持つ強力な価格決定力に自信を示している、というのが現状です。
フェラーリは、伝統と革新、限定性と成長という相反する要素を巧みに両立させることで、ラグジュアリー市場における独自の地位を確立し続けており、その揺るぎないブランド力と戦略的な経営手腕は、今後も持続的な魅力と成長を投資家にもたらすものと認識されています。
まとめ:もっと簡単にフェラーリの業績を述べるならば?
さらに簡潔に近年のフェラーリの業績や成長の軌跡を述べるならば以下の通りです。
- 株価は10年でほぼ10倍
- 販売台数は10年でほぼ2倍
- 販売台数の伸びよりも利益の伸びのほうが大きい→1台あたりの利益、ライセンス収入などが増加
- 1モデルあたりの構成比は20%以内
- 新車注文の8割は既存顧客向け、よって一見さんは残り「2割」の枠を争わねばならない
- 直近だと販売台数を絞り希少性を強める方針を採用、一方で限定モデルの比率が高くなり1台平均あたりの売上高が大きく上昇
- さらにはオプション、パーソナライゼーションサービスの拡充によって非限定モデルの販売単価と利益も大きく上昇
- 中国依存の姿勢を弱め、中国には「意図的に」売らない
- ニューモデルによって「新しい顧客を呼び込みつつ」も新規フェラーリ組の比率を一定以内にとどめることで「シームレスに、混乱なく顧客の若返りを図る」
- ハイブリッドなど電動化モデルは「儲かる」
- 「儲かる」ハイブリッドモデルの比率を徐々に拡大し、さらに収益性の向上を図っている
- 「製品ポートフォリオ」「顧客の構成」「電動化へ向けたシフト」「利益」など、すべては完璧に計算された戦略によってコントロールされている
合わせて読みたい、フェラーリ関連投稿
-

-
フェラーリの「現在のオーナー」は誰なのか?現在のフェラーリは「株主」によって所有されており、「フェラーリを買えずともフェラーリを所有できる」
| 「フェラーリという会社は誰のものか?」という問いの意外な答え | そう多くはない金額にてボクらはフェラーリを所有できる さて、フェラーリはエンツォ・フェラーリによって設立された自動車メーカーですが ...
続きを見る
-

-
フェラーリとV12エンジンとの歩みを見てみよう。初期の「コロンボ」「ランプレディ」エンジンから現在のF140系に至るまで、そしてその特徴とは
| フェラーリは小排気量V12エンジンを搭載しはじめてル・マンで優勝した自動車メーカーである | フェラーリはこれまでにも様々なV12エンジンを開発している さて、フェラーリの歴史を語る上で外せないの ...
続きを見る
-

-
「北の教皇」とまで呼ばれ、その権力を絶対的なものとしたエンツォ・フェラーリ。どのような名言を残し、どのような哲学を持っていたのか?
| エンツォ・フェラーリは「時代の50年以上先を行く」ビジネスマンであった | その存在は「神」にも等しく、今もその教えが根付いている さて、フェラーリ創業者であるエンツォ・フェラーリはまことに不思議 ...
続きを見る
参照:Ferrari