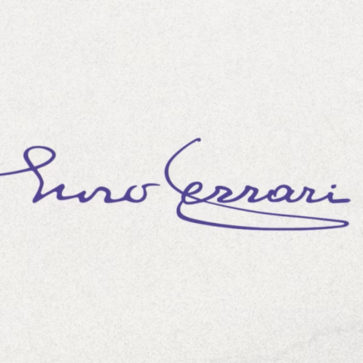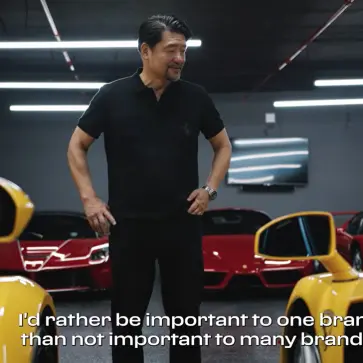| フェラーリとピニンファリーナ:名門タッグの終焉 |
フェラーリの革新への意欲:EVと新技術にも挑戦
イタリアのデザインハウス、ピニンファリーナとフェラーリとは長い間密接な提携関係にあり、両者の仲は「切っても切れない」と思われていたものの、2013年には突如としてフェラーリがピニンファリーナとのパートナーシップを解消し、この決断は自動車業界に大きな衝撃を与えています。
両者のコラボは60年以上のも長きにわたって継続し、フェラーリはピニンファリーナとともに数々の伝説的なモデルを生み出してきたことでも知られていますが、いったい当時何が起きていたのかを見てみましょう。
-

-
フェラーリがピニンファリーナ・デザインを振り返る。1951年から60年以上にわたる協業の歴史の中でとくに印象に残るモデル7選
| すでにパートナーシップは解除されているといえど、現代のフェラーリが持つ要素の多くはピニンファリーナが作り上げたものだった | ときどき、フェラーリのデザインがピニンファリーナでなかったら、と考える ...
続きを見る
ラ・フェラーリ開発が転機に:社内デザインが選ばれた理由
現在フェラーリのデザインを行うのはインハウス(社内)のデザインスタジオ、「チェントロ・スティーレ(デザインセンターという意味のイタリア語)」。
このチェントロ・スティーレのデザイン責任者、フラヴィオ・マンゾーニ氏が、その経緯をカーメディアのインタビューにて明かしていますが、そのきっかけとなったのは「ラ・フェラーリの開発」だったのだそう。
ピニンファリーナがデザインした最後のフェラーリはF12ベルリネッタ(2012年発表、2017年まで生産)だとされ、しかし実際に分岐点となったのは2013年に発表されたラ・フェラーリ(LaFerrari)の開発時。
-

-
フェラーリが自ら「今でも究極の跳ね馬です」と語るラフェラーリ。初のハイブリッド採用、F1と同様の設計を持つカーボンモノコックなどその理由に迫る
| ラフェラーリはそのデザイン、パワートレーン、そして思想などすべてが「新しい時代へと」向っている | そしてその存在はフェラーリのDNAを過去と未来とに「橋渡し」する役割を担っている さて、フェラー ...
続きを見る
フラビオ・マンゾーニ氏によると、ラ・フェラーリの企画当初、社内チームとピニンファリーナの両方にデザイン案の提出が求められ、経営陣が最終決定を下す形式だったとのこと。
結果として選ばれたのはフラビオ・マンゾーニ氏率いる社内チームの案であり、これがピニンファリーナ時代の終わりを意味することになったのだと説明されています。
-

-
フェラーリが288GTO、F40、F50、エンツォフェラーリ、ラフェラーリ、F80「ビッグシックス」の初期デザインスケッチを公開。市販車ではどう変わったのか
| フェラーリのスーパーカーは文字通り「伝統と革新」の象徴であり、その時代においての「フェラーリ」を体現している | そしてフェラーリのスペシャルモデルは「全て並べてみて」はじめてその考え方を理解でき ...
続きを見る
フェラーリに「自社デザインセンター」が必要だった理由
「60年以上の協力関係の後にピニンファリーナがその事実を受け入れるのは非常に困難でした。しかし、それは必要な決断でした。なぜならフェラーリは、唯一社内デザイン部門を持たない自動車メーカーだったからです。それは異常であり、リスクでもありました。」
フラビオ・マンゾーニ氏は当時を振り返ってこう語り、加えて、現代のハイパフォーマンスカー開発では技術的複雑性が急激に増しており外部デザイナーとマラネロのエンジニアが離れて作業するのは非効率になっていたといいます。
-

-
【動画】フェラーリのデザイナー、SF90スパイダーを語る。ピニンファリーナ時代からどう変わったのか、デザイナーの個性や近代フェラーリのデザインについて考える
| ボクはピニンファリーナよりもフェラーリ内製のデザインを支持している | さて、フェラーリが公式にて、チーフデザイナーであるフラビオ・マンゾーニ氏を起用した「SF90スパイダーのデザインについて語る ...
続きを見る
これは十分に理解ができる話でもあり、ブガッティも過去には「デザインとエンジニアリングが不可分なデザインに突入した」とも述べ、デザインがエアロダイナミクスや冷却などパフォーマンスに影響する範囲があまりに大きくなり、車体デザインと車両の設計は同時に行われなければならない、とも主張していますね。
-

-
ランボルギーニがEV計画を「白紙撤回」。ハイブリッド回帰で内燃機関の魂を死守、「EV開発はお金のかかる趣味であり、企業として正しくありません」
| ランボルギーニが「まさかの」電気自動車計画を撤回 | EVの発売を推し進めるフェラーリとは全く異なる展開に ランボルギーニが長年進めてきた「完全電気自動車(EV)」の開発計画を白紙に戻すという衝撃 ...
続きを見る
ただ、「フェラーリのデザインを一手に引き受ける」ことで名を知られるようになり、信用を得ていたピニンファリーナにとって「フェラーリとの決別」は(フラビオ・マンゾーニ氏が語るように)容易ではなかったのだと思われ、これは同時に「世界の富裕層から受けていた、フェラーリのワンオフモデルの受注」を失う可能性をも示唆しています。
実際のところ、ピニンファリーナにとって「フェラーリとの契約内容そのものは”屈辱的(あるいは隷属的)”なものであった」そうですが、それでもフェラーリとの関係性を継続していたのは「フェラーリという金看板にあやかる必要があったから」だとされていますね(2005年にピニンファリーナはインド企業、マヒンドラに買収されている)。
-

-
フェラーリがレッドドットアワードにてプロサングエ、ヴィジョンGT、296GTSがそれぞれ受賞したと発表!現代フェラーリのデザインはピニンファリーナ時代からこう変わった
| 時代に合わせてそのデザインが大きく変わりつつも、誰が見ても「フェラーリ」だとわかるデザインを維持していることに驚かされる | そしてピュアエレクトリック時代のフェラーリのデザインは更に大きく変化し ...
続きを見る
デザイナーとエンジニアの“共創”が求められる時代へ
かつて自動車メーカーは「車体とエンジン」を作り、その後に架装業者がボディを被せるといった手法が取られていたものの、その後「車体とボディが一体化した」モノコックが登場して大きく車両全体のデザイン・設計・生産工程が代わり、されに現代ではもうひとつ進化の場面を迎えたといっていいのかも。
こういった事情もあり、フェラーリのデザインは現場と密接にリンクする必要性から、社内化が不可避だったことがわかります。
「毎日のようにエンジニア、空力専門家、経済アナリストとデザイナーが会議を行い、段階的に最適な形状を導き出しています。これは最高のパフォーマンスを実現するために必要不可欠なのです。」
フェラーリの未来とフラビオ・マンゾーニ氏の挑戦
2010年にフェラーリへ加わったマンゾーニ氏。
当初は「大きなプレッシャーがあった」と語りますが、現在ではフェラーリの躍進の立役者として高く評価されています。
2015年の上場以降、フェラーリの企業価値は9倍近くに成長し、2023年には初のSUV「プロサングエ」を発表、2026年には初のEV(電気自動車)の投入計画も。
そしてEVではガソリン車とは全く異なる車体構造を実現でき、これがデザインに及ぼす影響は「今までの常識の範囲を超える」とも考えられ、EVの時代になると今まで以上に「デザインと車体設計の現場」との密接な関係性が要求されることになるのは明らかでです。
「新技術を扱うプロジェクトは常に挑戦です。たとえば、ハイブリッド・フェラーリの開発では、構成要素のレイアウト自体が新しいものでした。新しい技術は常に進化と革新の機会をもたらします。」
まとめ:ピニンファリーナとの別れはフェラーリ進化の始まりだった
60年にわたる協力を終え、フェラーリは自らの手でデザインと革新を追求する道を選び、その決断はプレッシャーを伴いながらも、現在の成功へとつながっています。
フラビオ・マンゾーニ氏は今後の技術革新についても前向きな姿勢を見せていますが、EV時代を迎える今こそ、フェラーリの新しいデザイン哲学が試されるときだと言えそうですね。
あわせて読みたい、フェラーリ関連投稿
-
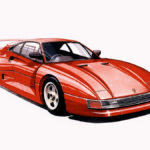
-
フェラーリF40の初期デザインスケッチは実際の市販車とは似ても似つかないスタイルだった。そのイメージは288GTO エボルツィオーネ、それがなぜ変更されたのかは謎である
Image:Ferrari | フェラーリF40は様々な意味において「特別」なクルマであった | 今見るとこのフェラーリF40の初期デザインスケッチは「レトロ」である さて、フェラーリが公式Faceb ...
続きを見る
-
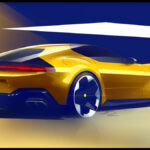
-
フェラーリ「12チリンドリでは、急進的で破壊的なデザイン手法を採りました。なぜならV12フロントエンジンモデルはいまやパフォーマンス面でのフラッグシップではないからです」
Image:Ferrari | 今やパフォーマンス面だと、V6/V8ミドシップのほうが優れ、パワーにおいてはV8ハイブリッドのほうがV12の上を行く | よってフェラーリはV12フロントエンジンモデル ...
続きを見る
-

-
フェラーリのデザインはこう変化した。1947年の創業時から最新のプロサングエまで、リトラクタブルヘッドライトやハンマーヘッドなどこんな変遷を遂げている【動画】
Gravity | この動画では、短時間でグラフィカルにフェラーリの変遷を見ることが可能となっている | 当然ではあるが、フェラーリのデザインはずいぶん大きな変化を遂げてきた さて、Youtubeチャ ...
続きを見る
参照:Motor1