
| アストンマーティンは7度の倒産を経て現在に至る |
それでも度重なる救済を経て存続しているということは「それだけ強いブランド力を持つ」ことにほかならない
英国を代表する高級自動車メーカー、アストンマーティン。
その110年以上にわたる歴史は、度重なる経営危機と、それを乗り越えてきた不屈の精神の物語です。
幾度となく復活を繰り返すことができたのは「単なる製品の物理的価値を超え、時代を超越した文化的資産によって形成されてきたブランドアイデンティティ」によるものだと考えていますが、ここではアストンマーティンの創業から現在に至るまでの歴史を、経営戦略、製品開発、文化的側面、そして将来展望という多角的な視点から詳細に分析し、その強さの秘密に迫り、いかにして過去の遺産と調和し、未来を切り開こうとしているかを考察したいと思います。
第1章:創業黎明期から戦前までの苦難とアイデンティティの形成
アストンマーティンの物語は、1913年にロンドンでライオネル・マーティンとロバート・バンフォードによって設立された「バンフォード&マーティン社」に始まります 。
当初のエンブレムは、創業者たちのイニシャルである“A”と“M”を組み合わせたシンプルなモノグラムで、社名の「アストン」は、創業者のマーティンが勝利を収めたヒルクライムレース「アストン・クリントン」に由来し、そこへ自身の名「マーティン」と組み合わせることで、「アストン・マーティン」というブランドが誕生したわけですね 。
そしてこの事実は、同社のアイデンティティが創業当初からレースと深く結びついていたことを明確に示しています。
-

-
アストンマーティンが10年ぶりにエンブレムのデザインを変更!シンプルで柔らかく、1970年代の「グリーンボックス」復活。これまでの変遷も見てみよう
| このウイングは古代エジプトにて復活のシンボルだとされた「スカラベ(フンコロガシ)」をイメージしている 現代のウイングエンブレムが見られるようになったのは1932年から さて、アストンマーティンは昨 ...
続きを見る
そこからの道のりは平坦ではない
しかし、その道のりは決して平坦ではなく、創業時の象徴的なモデルとして1915年に設計された車両はコヴェントリー・シンプルックス製の1.4リッター4気筒エンジンとイソッタ・フラスキーニ製のシャシーを採用し、高い性能を目指して開発されたものの、第一次世界大戦の影響で生産には至らなかったという悲劇に終わっています。
戦後に入ってもアストンマーティンは度重なる財務的困難に直面し、特にモータースポーツへの多額の投資や経営効率を顧みない(こだわりの)生産方式が財務を圧迫し続けることに。
1924年には、創業を支援していたズボロフスキー伯爵がレース中の事故で亡くなったことを受けて一度目の倒産を迎え、そして、その翌年の1925年にも再度倒産し、ここで創業者マーティンは会社を去ってしまいます。
その後、アウグストゥス・チェーザレ・ベルテッリが経営に参画し、インターナショナルやアルスターといった名車を生み出すことでブランドの名声を高めることに成功するも、1932年には再び経営危機に陥るなど、その脆弱なビジネス構造はここでも改善されず。
第二次世界大戦が勃発すると、アストンマーティンは高級スポーツカーの製造を停止し、軍用機の部品製造に専念することで戦火を生き延びることに成功します 。
アストンマーティンは「倒産と救済」を幾度となく繰り返す
この創業黎明期から戦前までの歴史は、アストンマーティンブランドに深く刻まれた構造的な矛盾を浮き彫りにしていて、それは「モータースポーツでの栄光」という技術的アイデンティティと「ビジネスとしての脆弱性」という経営課題の狭間での揺れ動き。
レースでの成功がブランドの技術的アイデンティティを確立する一方、それに伴う過大な投資が経営を圧迫し、破綻を繰り返すという矛盾した因果関係がこの時代に形成されたわけですね。
しかし、興味深いことに、その都度外部からの投資家が現れてブランドを救済しており、これは財務上の困難を補って余りあるほど、ブランド自体に強固な価値が内在していたことを示唆しています(アストンマーティンとは逆に、救済がなされずに消えていった自動車メーカーやコーチビルダーは数しれない。それはには「救うだけ」の魅力が存在しなかったのだと思われる)。
そしてさらに興味深いことに、この「倒産→救済」というパターンは、後の時代にも幾度となく繰り返されることになります。
合併・買収、そして法的な再建手続きの定義によっても判断が変わるために一概にその回数を算出することは非常に困難ではありますが、もしかするとアストンマーティンが「現存する自動車メーカーのうち、もっとも多くの倒産回数を経験した会社」なのかもしれません(その次はランボルギーニかもしれない)。
第2章:デイヴィッド・ブラウン時代の黄金期 –「DB」伝説の確立
第二次世界大戦後、アストンマーティンは再び存続の危機に瀕していたものの、この時代に現れた救世主が英国の実業家、デイヴィッド・ブラウン。
1947年、彼は「ザ・タイム紙」に掲載された広告をきっかけとしてアストンマーティン、そして同じく経営難に陥っていた高級車メーカー「ラゴンダ社」を買収していますが、この買収により両者は「アストンマーティン・ラゴンダ社」として新たなスタートを切ることとなり、同社はデビッド・ブラウンの豊富な資金力を背景に、ベントレーの直列6気筒DOHCエンジンを搭載した高性能スポーツカーの生産を再開しすることに成功します。
そしてこの新体制の象徴となったのが、デイヴィッド・ブラウンのイニシャルを冠した「DB」シリーズ 。
1948年にDB1が初めて登場したのを皮切りに、DB2、DB4、そして「最高傑作」と称されるDB5へと一貫したモデルラインナップが確立され、この時代には、ラゴンダのエンジニアであったW.O.ベントレーや、アウトウニオン・タイプDのエンジン開発に携わったエーベラン・フォン・エバーホルスト、そしてテッド・カッティングといった才能ある技術者が多く在籍し、製品の技術的卓越性を支えたひとつの「黄金時代」であるとも捉えられています。
アストンマーティンとモータースポーツとは「不可分」である
また、この時代にはモータースポーツへの本格的な復帰がなされており、1949年にはル・マン24時間レースに出場し、1959年にはDBR1がル・マン24時間レースで総合優勝を果たすなど、レースでの栄光がブランドの地位を不動のものとすることに。
この成功がアストンマーティンを再びレーシングブランドとしてのアイデンティティを確立する上で不可欠であったことは言うまでもなく、しかしこの黄金期の極致は、1963年に誕生したDB5によってもたらされます。
生産台数はわずか1,025台にとどまり、ほとんどが手作業で製造されたこのモデルは「稀少性と技術的完成度を両立」させており、そして何よりも1964年の映画『007 ゴールドフィンガー』でボンドカーとして採用されたことによって、アストンマーティンは「第一次絶頂期」を迎えることになったわけですね。
デイヴィッド・ブラウン時代は、単に経営を立て直しただけでなく、「DB」という一貫した製品ラインとモータースポーツでの栄光を融合させることで、アストンマーティンのブランドを象徴する普遍的な価値を確立した時期であり、この一貫した製品戦略と、技術への惜しみない投資、そしてモータースポーツでの勝利の連鎖がブランドイメージの向上と絶頂期をもたらしたのだと解釈されています。
実際のところ、この時代の遺産は、その後の度重なる経営危機においても、アストンマーティンというブランドの核心として機能し続けており、それはすでに経営権を手放したデイヴィッド・ブラウンの名がいまなお新型車に用いられていることからも理解が可能。
つまり、そのイニシャルが単なるモデル名を超え、ブランドのDNAそのものになったことを物語っています。
| モデル名 | 生産期間 | 特筆すべき特徴 |
| DB1 | 1948~1950 | デイヴィッド・ブラウン体制下で初のモデル。 |
| DB2 | 1950~1953 | カロッツェリア・トゥーリングデザイン、スタイリッシュな進化。 |
| DB2/4 | 1953~1957 | 後部座席の追加、使い勝手の向上。 |
| DB Mark III | 1957~1959 | - |
| DB4 | 1958~1963 | 軽量ボディ構造「スーパーレッジーラ」採用。 |
| DB5 | 1963~1965 | 映画『007』ボンドカーとして有名、「最高傑作」と称される。 |
| DB6 | 1965~1971 | DBシリーズ最後の「偉大な3部作」の一台。 |
第3章:時代の波に揺れた暗黒期とフォード傘下での再興
デイヴィッド・ブラウンが経営から離れた1972年以降、アストンマーティンは再び暗黒時代へと突入することとなり、ブラウン・グループの経営不振によって、同社はわずか101ポンド(当時の為替レートだと約9万円)で売却されるという屈辱的な状況に陥っています。
オイルショック後の世界的な不景気、非効率な生産体制、そして時代遅れとなりつつあったV8エンジンへの依存といった構造的な問題が再燃し、会社は再び管財人の手に渡ることとなるのですが、この時期の年間生産台数は(驚くべきことに)わずか30台にまで落ち込んだという記録もあり、文字通りブランド存続の危機に直面した時期でもありますね。
そしてこの苦境から再び浮上するきっかけとなったのが「1987年のフォードによる買収」。
フォードは高級車ブランドを集めたPAG(Premier Automotive Group)の一員としてアストンマーティンを迎え入れ、その豊富な資金力と経営資源を注入し、この投資によってアストンマーティンは中長期的な視点での抜本的な改革、および現代的なモデルラインナップの拡充が可能となり、ほどなくしてブランド再生の象徴として登場したのがフォード傘下で初めて誕生したDBシリーズ、「DB7」です。
フォード傘下時代は、アストンマーティンが繰り返してきた「技術的卓越性vs財務的脆弱性」というサイクルを”大企業の資本と管理ノウハウ”で一時的に断ち切った重要な転換点であると捉えられており、この時期には12気筒モデルの開発やDBシリーズの復活が果たされ、アストンマーティンは「第二次絶頂期」を迎えることに。
しかし2007年にはフォード自身の経営悪化を背景に、アストンマーティンはデイビッド・リチャーズ率いるコンソーシアムに売却され、フォードグループから離脱することになるのですが、売却後もフォードは資本の一部を保有し、協業関係は維持されたままとなっています。
この一連の歴史は、アストンマーティンが自社単独では大規模な投資や抜本的な改革が難しい小規模メーカーであって、その存続が常に外部からの資本とリーダーシップに依存してきたことを示唆しており、これは現代の(後述する)ローレンス・ストロール体制でも見られる、ブランド存続のための重要なパターンであるとも考えられます(パトロンなしには成立しない)。
第4章:文化アイコンとしての地位確立 – 映画『007』との共鳴
アストンマーティンの歴史を語る上で外せないのが映画『007』シリーズとの関係性。
このパートナーシップは単なる製品プロモーションを超え、ブランドの文化的資産を確立する上で決定的な役割を果たします。
その始まりは(上で述べた)1964年のシリーズ第3作『ゴールドフィンガー』で、アストンマーティンDB5がジェームズ・ボンドの愛車「ボンドカー」として登場したことにはじまりますが、 劇中ではこのクルマに対し、スパイ映画の代名詞とも言える防弾ガラス、機関銃、レーザーカッター、脱出(射出)シートといった特殊装備が加えられたことで、DB5は単なる乗り物から「究極のスパイ・ガジェット」へと昇華されたわけですね。
映画のヒットとともに、DB5は世界で最も有名な車の一つとなり、そのプレミア価値は急騰し、中古車市場で異常な値上がりを見せているのはご存知のとおりかと思います。
アストンマーティンは継続的に007映画とともに価値を高める
特筆すべきは、このパートナーシップが継続的にブランド価値を高めている点で、「映画の原作となるイアン・フレミングの小説だと「ジェームズ・ボンドの愛車はDBMk.III」であったものの、映画では当時の最新モデルであったDB5に置き換えられています。
これはアストンマーティンが常に革新的なイメージを追求してきたことを物語っており、その後の作品でも次々と「(原作同様のDBMk.IIIではなく)最新モデルを登場させる」ひとつの潮流を築いた事例なのかもしれません。
加えて、その後には同社のパーソナリゼーション部門の名称を(007映画のスパイ小道具開発部門である)「Q」としたり、限定モデルの生産台数を当時の最新007映画の作品本数(24本目)にちなんで「24台」としたり、さらにはハイパーカーカテゴリに参戦するに際しレーシングナンバーを「007」とするなど、両者の関係性はもはや切っても切れない状態にまで密接に強固に結びついています。
予断ではありますが、原作者イアン・フレミング自身がアストンマーティンDB2/4の初代オーナーであり、自身の車にさまざまな改造を施していたという事実もまた「フィクションと現実の境界を曖昧に」していて、このパートナーシップに格別のオーセンティシティ(本物らしさ)を与えている、と言われていますね。
さらに近年、アストンマーティンは「007エディション」といった限定モデルをリリースするなど、このパートナーシップを積極的に活用していますが、さらに、限定生産でDB5の「コンティニュエーション」モデルを復刻したりといった例もあり、これらは映画『007』がアストンマーティンに与えた影響が、単なる一過性のプロモーションではなく、ブランドの歴史と価値を永続的に高める文化的な資産であることを示しています。
歴代ボンドカー一覧
| 映画タイトル | 公開年 | 登場車種 |
| 007 ゴールドフィンガー | 1964 | DB5 |
| 007 サンダーボール作戦 | 1965 | DB5 |
| 女王陛下の007 | 1969 | DBS |
| 007 リビング・デイライツ | 1987 | V8 ヴァンテージ |
| 007 ゴールデンアイ | 1995 | DB5 |
| 007 ダイ・アナザー・デイ | 2002 | V12ヴァンキッシュ |
| 007 カジノ・ロワイヤル | 2006 | DBS |
| 007 慰めの報酬 | 2008 | DBS |
| 007 スカイフォール | 2012 | DB5 |
| 007 スペクター | 2015 | DB10 |
| 007 ノー・タイム・トゥ・ダイ | 2021 | DB5, DBS, V8, ヴァルハラなど |
Google スプレッドシートにエクスポート
第5章:現代の経営戦略 – ローレンス・ストロール体制下の変革
現代のアストンマーティンを率いるのは、2020年に株式を取得し会長に就任したローレンス・ストロール。
彼のビジョンは、過去の経営者たちとは異なり、ブランドの伝統と現代的なビジネスモデルを同時に追求することにありますが、この戦略の顕著な例がブランド初のSUV「DBX」の投入です。
高級自動車市場におけるSUVの需要拡大を背景としてDBXはアストンマーティンの経営健全化に不可欠な役割を果たすこととなり、現実的にDBXがアストンマーティン全体の販売台数の半数以上を占めるという事実によってその貢献度が明確されていて、(まだまだ先行きはわからないものの)これまでのアストンマーティンの”習慣”でもあった、「倒産→救済」というサイクルを断ち切ることができる可能性すら見えています。
アストンマーティンは再びモータースポーツに注力
そして現代アストンマーティンにおけるもう一つの重要な柱がF1ワークスチームとしての再参戦。
ローレンス・ストロールは、自身が経営難から救済したレーシング・ポイントF1チームを2021年から「アストンマーティンF1」へと名称変更し、これは単なるモータースポーツ活動ではなく、グローバルなブランド認知度の向上、新技術開発、そして顧客エンゲージメントを高めるための大胆なマーケティング戦略です(加えて、息子であるランス・ストロールをF1に参戦させるためのシートを確保する手段でもある)。
It’s a smooth opening lap for our cars, but we can’t say the same for Piastri who brings out a SC!
— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 21, 2025
Fernando is P11 and Lance is P13.#AzerbaijanGP pic.twitter.com/ORM8JO0p3R
-

-
アストンマーティンのボディ色に異変。「F1参戦後にレーシンググリーンの人気が高まって全カラーのうち12%を、グリーン系だけで24%を占めるように」
Astonmartin | さらにF1参戦によってアストンマーティンには多くの新規客がなだれ込む | もはやF1参戦による効果は疑う余地がない さて、アストンマーティンは「超高級、F1」を新しいブラン ...
続きを見る
ローレンス・ストロールは「投資家」であり、そのためには過去の経営者たちが直面した失敗から様々な教訓を学んでいることを伺え、たとえば伝統的なスポーツカー市場の縮小という課題に対してDBXという収益性の高いモデルで経営基盤を固める一方、F1参戦という大胆な戦略でブランドの技術的信頼性とグローバルな魅力を再構築しています。
これはブランドの価値を再定義し、危機を乗り越えるための現実的なアプローチであり、現時点では「有効に機能している」と考えていいかもしれません。
さらに付け加えるならば、直前のアンディ・パーマーCEOが「ランボルギーニやフェラーリ、マクラーレンに対抗しようとしていた」のに対し、ローレンス・ストロールは「それらとは対抗せず、”超高級なGT”という、アストンマーティンならではの独自の立ち位置を強化することで」プレゼンスを強化しようとしており、つまりは「排他性」「差別化」を重視した、投資家らしい論理的な戦略を採用しています。
| 戦略的要素 | 具体的な成果 | 影響 |
| DBXの投入 | この数年において、販売台数の半数以上を占める 。 | 収益の柱となり、経営健全化に貢献。ブランド初のSUVという市場参入で顧客層を拡大。 |
| F1ワークス参戦 | ブランド認知度の急上昇 。2025年9月現在、グランプリ出場142回、優勝1回、表彰台12回 。 | グローバルなブランド認知度向上。技術的信頼性を高め、高性能ブランドとしてのイメージを強化。 |
第6章:未来への挑戦 – 電動化と持続可能性
現代の自動車産業は電動化と持続可能性という大きな変革期を迎えていますが、アストンマーティンも例外ではなく、この波に乗り遅れまいと野心的な戦略を掲げています。
その中心となるのが「Racing.Green.」と名付けられたサステナビリティ戦略で、同社は、2030年までに製造施設をネットゼロにすること、2039年までにサプライチェーン全体をネットゼロにすることなど、具体的な目標を明記しています。
すでに、2019年以降、英国のすべての製造施設で再生可能エネルギーを100%使用しており、ウェールズのセント・アサン工場では1万4,000枚以上のソーラーパネルを設置する計画も進行中。
電動化へのロードマップも具体的に示され、2024年前半には初のプラグインハイブリッド車(PHV)『ヴァルハラ』を発売したほか、この数年内にはブランド初のバッテリー式電気自動車(BEV)を発売する計画も公表済み(BEVについては、当初2025年に発表する計画であったが、市場の状態を鑑み、後ろ倒しにすることがアナウンスされている)。
そして、2030年までには、主要な製品ラインナップを完全に電動化するという長期目標を掲げていますが、 (アストンマーティンのような小規模自動車メーカーにとって)この電動化戦略の実現には外部パートナーシップが不可欠であり、アストンマーティンは、メルセデス・ベンツAGとの関係を維持しつつ、BEV向けにパワートレーン・コンポーネントを供給する長期的な戦略的供給契約を(米新興EVメーカーである)ルシードと締結済み。
-

-
アストンマーティン「我々の顧客の中には”EV否定派”が存在します。ガソリンエンジンを廃止することで彼らを怒らせるのは得策ではありません」
| 結果的にアストンマーティンはEVへのシフトを当初の計画から最長で5年遅らせることに | そして「市場と顧客、バッテリー技術」のバランスを見ながら初のEVを投入するようだ アストンマーティンは電動化 ...
続きを見る
この戦略は、内燃機関(ICE)の技術はメルセデスAMGに依存し、次世代のBEV技術はルシードから供給を受けるという、賢明な「二本立て」モデルということを意味しており、さらに電装品や一部コンポーネントについては中国の吉利汽車から供給を受けるという契約を結ぶことで、アストンマーティンは「資本をスポーツカーへと」集中させることが可能となっているわけですね。
-
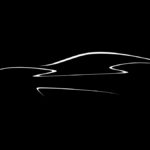
-
アストンマーティンが「まさかの」米ルシードとの提携を発表。ルシードの技術を使用しエレクトリック「ハイパーカー、スポーツカー、GT、SUV」を開発
| アストンマーティンは内燃機関に固執するかのように見えたが、2030年までにはピュアEV中心のラインアップへ移行するようだ | それにしてもまさかルシードと提携するとは予想だにしなかった さて、アス ...
続きを見る
これは、伝統的な技術力を維持しながら、電動化という巨額の投資が必要な分野において他社に依存することによりリスクを分散させるという、小規模メーカーならではの現実的な生存戦略であると考えられ、以前のアストンマーティンであれば、これ(電動化分野)についても”自力”でなんとかしようとし、また(資金難によって)倒産していたのかもしれません。
-

-
アストンマーティン「今後、中国の吉利汽車からシートやエアコン関連の供給を受ける」。開発速度向上とコスト削減を主眼に大きく方向性をシフト
| ただしそれも「既存ラインアップを入れ替え終わるまで」のことだと思われる | 現在、アストンマーティンはそのラインアップを刷新することが最大の課題である さて、先日はニューモデル「DB12」を発表し ...
続きを見る
| 目標年 | 電動化・サステナビリティ目標 |
| 2024年(前半) | 初のプラグインハイブリッド車『ヴァルハラ』発売 |
| 2026-2027年 | 初のバッテリー式電気自動車(BEV)発売 |
| 2030年 | 製造施設をネットゼロに 、主要ラインナップを完全に電動化 、サプライチェーン排出量を30%削減 |
| 2039年 | サプライチェーン全体をネットゼロに |
結論:伝統と革新の狭間で – アストンマーティンの未来展望
創業以来、アストンマーティンは幾度も経営危機に直面しており、しかしその都度、外部からの強力な資本とリーダーシップによって救済され、ブランドとしての価値を再定義してきたという稀有な歴史を持っています。
この歴史が示すように、アストンマーティンが存続し続けてきた最大の理由は、モータースポーツに根差した「高性能」、そして英国らしい「気品」という独自のブランドアイデンティティが常に熱狂的な支持者を引きつけてきたからに他なりません。
デイヴィッド・ブラウンによる黄金期、フォード傘下での再興、そして現代のローレンス・ストロール体制は、それぞれが異なる形をもってこのブランドの価値を再定義し、危機を乗り越えさせてきたことがわかるかと思いますが、特に映画『007』シリーズとのパートナーシップは物理的な製品価値を超えた文化的資産となり、ブランドのレジリエンス(回復力)の源泉となっています。
そして現代の経営戦略は、過去の教訓を活かしつつ、DBXという収益の柱を立てて経営を安定させ、F1ワークスチームとしての活動によってブランドの技術的威信を高めるという収益とブランド価値の両立を目指す現実的なアプローチを実践しているほか、さらに電動化という未来の課題に対しては、ルシ-ドやメルセデス・ベンツといった外部の強力なパートナーシップを賢明に活用することで自社のコアコンピタンスであるデザインとブランド力を活かしつつ、巨額な投資リスクを分散させようとしていることもわかります。
-

-
アストンマーティンが「ベントレーのCEO」を迎えた半年後、新戦略を次々発表。「ポルシェ911を参考にしたバリエーション強化」「MTの復活」
| ここまで具体的、かつ競争力のある戦略を発表したアストンマーティンCEOは存在しなかった | この独自性のあるプランに基づいた成長には期待したいところである さて、様々なカーメディアが報じている「ア ...
続きを見る
今後も、アストンマーティンは伝統的な内燃機関の遺産と、革新的な電動化技術の融合という難しい課題に直面し続けることは間違いなく、しかし、その歴史が証明するように、変化に対応する柔軟性と揺るぎないブランドアイデンティティを武器として、その孤高の英国流儀を継承していく可能性が高い、と思われます。
このブランドの将来を評価する際には、単なる財務諸表だけでなく、その文化的資産、そして現代の経営戦略が過去の教訓からいかに多くを学んでいるかという視点から多角的に分析することが不可欠であり、そして「客観的に見ても」現在のアストンマーティンの経営体制が最も安定しており、そして未来へ向けての高い成長力を持っているのではないかとも思われます。
-

-
アストンマーティン「今後の計画にセダンは一切含まれません。我々の超高級化・超高性能化戦略において、セダンは必要ではないのです」
| アストンマーティンはその方向性を大きくシフト、1台あたりの利益を最大化する方向へ | それでもアストンマーティンが「セダンを廃止する」というのは大きな驚きでもある さて、アストンマーティンは今月2 ...
続きを見る
あわせて読みたい、関連投稿
-

-
ロールス・ロイスとベントレー:かつては同門、しかし袂を分かつことで双璧をなすようになった英国高級車の知られざる歴史と違いとは
Image:Rolls-Royce | はじめに:英国高級車の二巨頭、ロールス・ロイスとベントレー | かつて両ブランドは「70年以上も」同じ企業による「異なるブランド」であった 自動車の世界には、た ...
続きを見る
-

-
マクラーレンの歴史:レースと革新が織りなす究極のパフォーマンスへ、ニュージーランドの若き才能が蒔いた種が世界のモータースポーツの頂点に
| 多くの有名なスポーツカーメーカーは「創業者一族」の手を離れている | マクラーレンもまた「第三者の手に渡りつつ」しかしそのDNAを失っていない さて、歴史あるスポーツカーメーカーというとロータス、 ...
続きを見る
-

-
英国伝統の自動車メーカー、ロータスの誕生から現代に至るまでの歴史を考察。コーリン・チャップマンの残した功績はあまりに大きく、しかしその天才性に依存しすぎた悲運とは
| 「ロータス」は創業者であるコーリン・チャップマンの画期的な思想によってその名を知られるように | とくに「軽量」「ハンドリング」はそのブランドの”核”である 自動車の世界において「ロータス」という ...
続きを見る






















