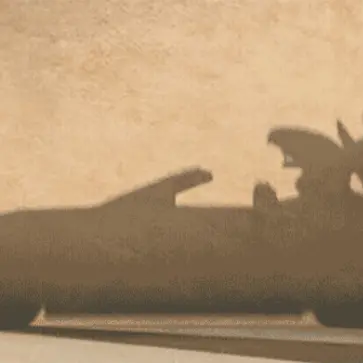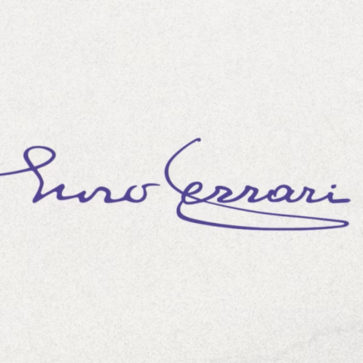| 一方、エンツォ・フェラーリは「4シーターのファン」であった |
フェラーリはプロサングエをけして「SUV」とは呼んでいない
さて、フェラーリの前CEO、セルジオ・マルキオンネ氏は「もしフェラーリが4ドアを作ろうとでも言い出したならば、自分を撃ち殺してくれてもいい」と語っています。
ただ、時代が変わって2022年9月、フェラーリはついに「初の4ドア」となるプロサングエを発表していますが、今回はそのプロサングエの開発に関わる秘話が公開されることに。
エンツォ・フェラーリは「4ドア」フェラーリには反対だった
フェラーリ創業者、エンツォ・フェラーリは「自分のクルマ」として4シーターを好んだといい、最初に選んだフェラーリの”自家用車”は1960年製の250GT 2+2。
一方で「4ドア」フェラーリに対しては否定的な見解を示していて、1980年にピニンファリーナが4ドアを持つデザインスタディ「ピニン(Pinin)」を発表した際にはこれを否定しており、その理由は「フェラーリはドライバーにフォーカスすべきだから」。
Image:Ferrari
たとえ2+2といえど、2ドアクーペであれば「主役はドライバー」であるものの、同じ4座であっても、ドアが4枚となれば「場合によっては主役が後席に座る人」となってしまうことを懸念したのかもしれません。
実際のところ、この「ピニン」以降、エンツォ・フェラーリが存命であった頃に「4ドアフェラーリ」が議論されることはなかったといいますが、エンツォ・フェラーリが現役であった時代では「330 GT 2+2」、「モンディアル」、「456GT」、そして没した後にも「612スカリエッティ」「FF」「カリフォルニア」「GTC4ルッソ」「ポルトフィーノ」「ローマ」等といった4シーターが発売されており、フェラーリがずっと4シーターを重視し続けてきたことがわかります。
フェラーリ・プロサングエの開発は困難を極める
今回フェラーリが公開したコンテンツでは、「どうやってプロサングエ(4ドアフェラーリ)の発売にゴーサインが出されたのか」については触れられておらず、しかし「顧客の多様化」がひとつの起点となったもよう。※顧客がフェラーリに求める要件が変化してきたのだと思う
ただ、フェラーリは「4ドア」「車高が高いクルマ」を発売した経験がなく、よって「(乗り降りしやすいよう)高いヒップポイント」「(どんな環境においても底を擦らない)高い最低地上高」を盛り込むとなると、フェラーリがもっとも重要視する「ドライバーとのエンゲージメント」に大きな課題が生じたと述べています。
この課題とは(高い重心による)姿勢変化や、これまでにない重量配分であったと思われますが(2名乗車時と、4名乗車+荷物フル積載時の重量バランス変化への対応にも苦労したと言われる)、これを解決するためにはまずサスペンションの新規開発からはじまったといい、提携関係にあるマルチマチック社と共同にてプロサングエのサスペンションを設計することに。
そしてスポーツカーとは全く異なる挙動を「スポーツカーのように」手懐けるために開発されたのが新しいアクティブサスペンションで、この要となるのはモータースポーツからフィードバックを受けた「スプールバルブ」技術。
これは48Vシステム下で作動するもので、「車体制御と乗り心地」を両立させるほか、既存のアクティブサスと比較して軽量コンパクト、さらにはアンチロールバーも不要となるのだそう(SUVの車体制御に、従来の高級車に採用される技術ではなく、モータースポーツ由来の技術を取り入れるところがフェラーリらしい)。
フェラーリはプロサングエにおいてもエアロダイナミクスを追求
そのほかフェラーリらしい点といえば「エアロダイナミクス」を挙げることができ、たとえば「エアダクト」「エアロブリッジ」、そして最も特徴的なのは「ホイールアーチ」。
このホイールアーチはオフローダーによく見られる「(タイヤが跳ね上げる泥や石からボディを守る)フェンダーモール」のように思えますが、このアーチはボディに貼り付けたものではなく「フロート」しており、空気の通り道(エアチャンネル)を設けることでエアカーテン効果を獲得しています。
つまるところ「そのデザインと機能とが密接に結びついている」「課題のソリューションに対し、モータースポーツ由来の技術を活用している」のがプロサングエということになり、こういったディティールを見てゆくと、フェラーリが「プロサングエはSUVではない」と主張することにも納得がゆきますね。
フェラーリは多様化する顧客ニーズに対応
逆に「フェラーリらしくない(これまでのフェラーリに見られない)」のはもちろん「4ドア」という構成で、しかしフェラーリは後部ドアに(ファミリーカー的ではなく)エキゾチックな観音開き構造を採用しており(ウエルカムドアと呼ばれる)、このドアは(他の観音開きドア採用車とは異なり)フロントドアを開けずとも開閉が可能な構造を持っていて、しかも「電動開閉式」。
さらに後席はなんと「マッサージ機能つき」、リアのラゲッジスペースは473リッターという広大な容量を誇っており、フェラーリらしい思想と機能に加え、これまでのフェラーリにはない利便性と快適性をプラスしたのがこのプロサングエということになるのかもしれません。
おそらくフェラーリはこのプロサングエを「フェラーリオーナーの日常の足(さすがにスーパーカーを毎日乗ることは難しい)」として提供しようという考えがあったのだと思われますが、現時点では「プロサングエの購入者の70%がはじめてフェラーリを購入する人々」だとされ、フェラーリの客層を大きく拡大することに貢献したクルマであるとも考えられ、いかに多くの人々がプロサングエのようなクルマを待ち望んでいたかもわかります。
一方、こういったSUVの投入はスポーツカーメーカーにとって諸刃の剣でもあり、顧客ベースを拡張する事ができる一方、ブランドイメージを希薄化したり既存ファンを遠ざけることがあり、よってポルシェはカイエン発売時にも「SUV」とは呼ばずにラリー(モータースポーツ)の歴史を引用して「スポーツカー」であることを強調し(いまではSUVという呼称を用いている)、ランボルギーニはウルスについて(SUVと呼ばれることを避けられないと判断したのか)「SSUV(スーパーSUV)」と主張したことも。
そしてフェラーリもまた、上述の通りプロサングエを「SUV」とは呼んではいませんが、フェラーリにてチーフ・マーケティング&コマーシャル・オフィサーを務めるエンリコ・ガリエッラ氏は以下のように語っています。
「我々としても、プロサングエをどう分類するべきか社内でも議論を重ねたのですが、結果的に、プロサングエは「プロサングエ」という独自のセグメントに属する固有種であるという結論に達しました。」
合わせて読みたい、フェラーリ関連投稿
-

-
リチャード・ハモンドがフェラーリ・プロサングエに試乗し珍しく辛辣なコメント。「この金額を支払うのであれば、ルノーのSUVと家を買ったほうがいい」【動画】
| フェラーリを悪くいうとフェラーリから冷遇される可能性も | このボディカラーはなんとなくアッズーロ・ディーノっぽいが さて、元「トップギア」のホスト、リチャード・ハモンドがフェラーリ・プロサングエ ...
続きを見る
-

-
フェラーリが「左右非対称ストライプ」を用いたカスタム仕様のプロサングエを公開。その仕様はまさに「クラシックエレガンス」
Image:Ferrari | 今後はプロサングエの「テーラーメイド」仕様が増えてくるものと思われる | 「プロサングエにストライプ」はなかなか新鮮 さて、フェラーリが自社のパーソナリゼーションプログ ...
続きを見る
-

-
もう手が入ってないところを探すほうが難しい。マンソリーによるフェラーリ・プロサングエの「フルカスタム」が凶悪すぎる
| それでもこういったカスタムは「けっこうな需要がある」ものと思われる | おそらくプロサングエのオーナーの多くは「フェラーリのカスタム」に抵抗を感じないのかも さて、マンソリーはフェラーリ プロサン ...
続きを見る
参照:Ferrari